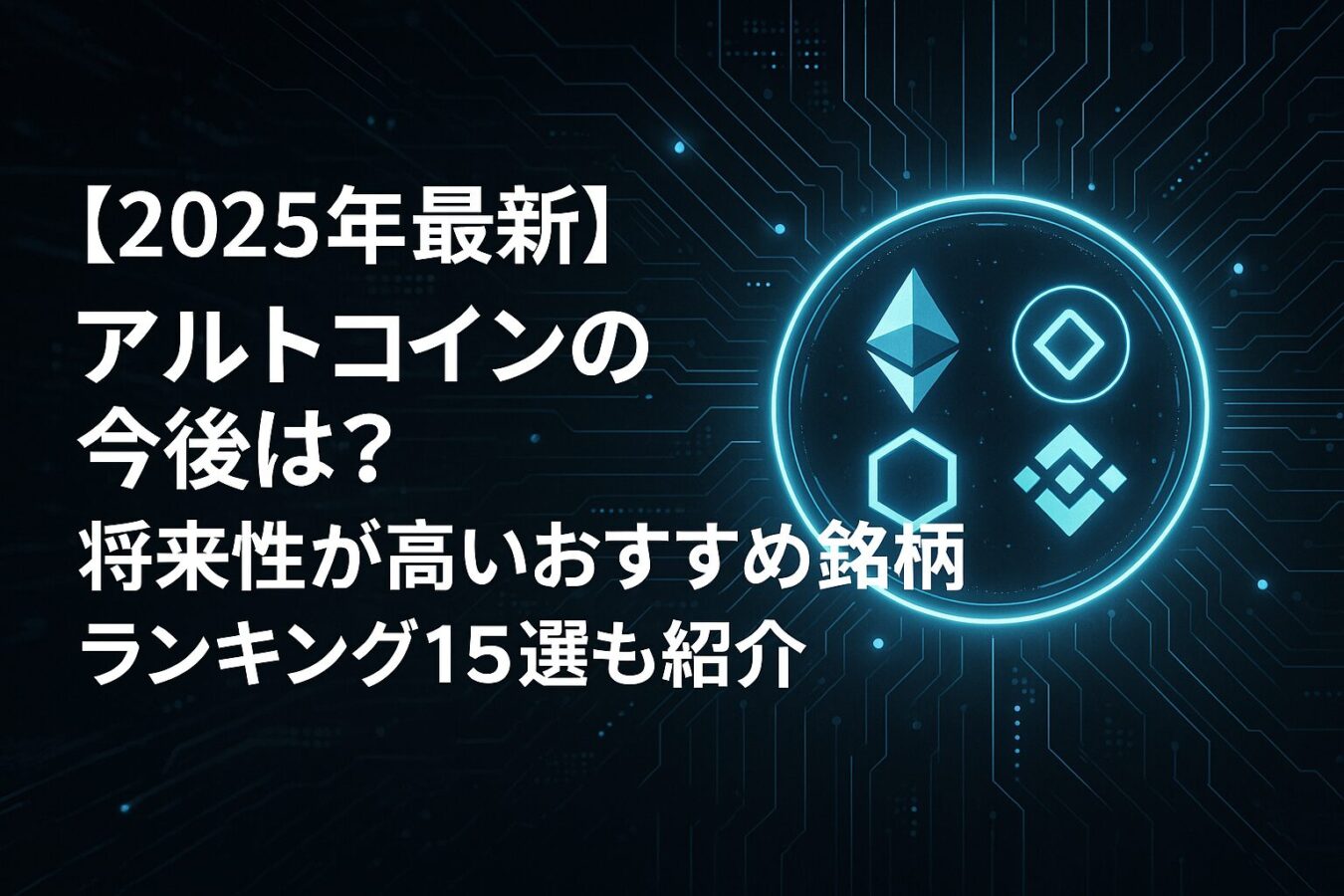アルトコイン市場は、ビットコインに続いて急速に成長しています。
数あるプロジェクトが新技術を開発し、NFTやDeFiといった領域で注目を集めてきました。
その一方で、価格変動が激しく、どの銘柄を選べばよいか迷う人も多いでしょう。
本記事では、2025年時点で期待されるアルトコインの今後を総合的に解説します。
市場動向を踏まえたランキング形式で有望銘柄を紹介し、選び方や購入に適した取引所も解説します。リスクとメリットを把握し、賢く投資を検討したい方はぜひ最後までご覧ください。
早速、オススメのアルトコイン15選を見たいという方はこちらから当該見出しをご覧ください!
アルトコインとは?
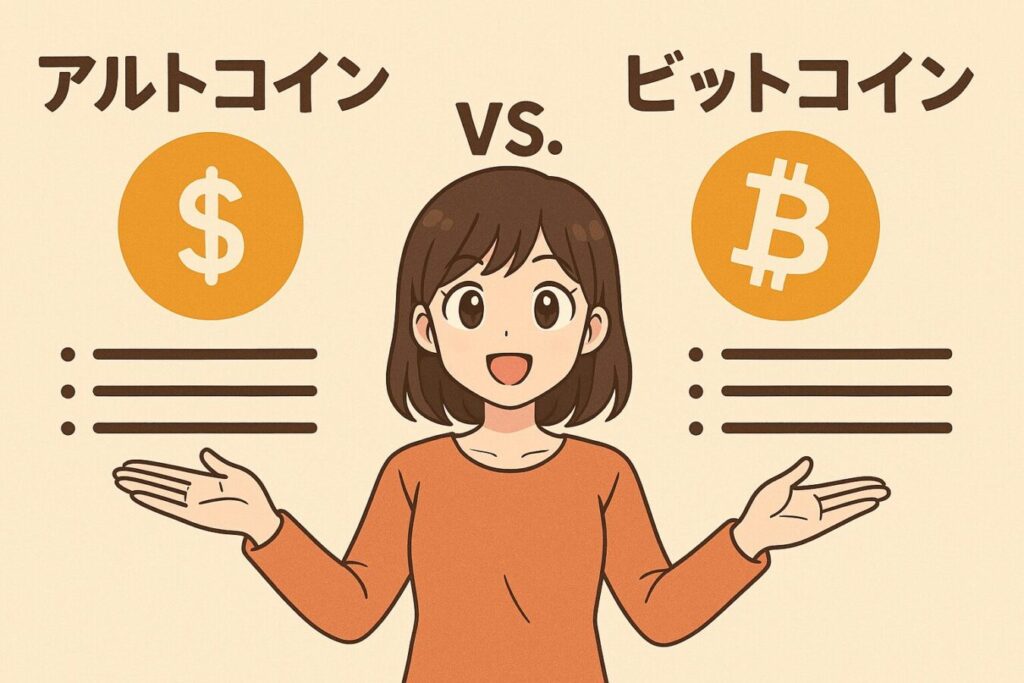
アルトコインとは、ビットコイン以外の暗号資産(仮想通貨)を総称した呼び名です。
「Alternative Coin」の略で、文字通り「代替となるコイン」を意味します。
ビットコインが暗号資産の先駆けであるのに対し、アルトコインはその後に登場した多種多様なプロジェクトを指します。
実際に存在するアルトコインは数万種類とも言われ、その数はさらに増加傾向にあります。
代表的なアルトコインの例として、イーサリアム(ETH)やエックスアールピー(XRP)などが挙げられます。
これらは、国際送金やスマートコントラクトなど固有の用途や技術を持ち、ビットコインとは異なる価値を提供しようとしています。
アルトコインの中には、時価総額が大きく流動性が安定しているものもあれば、極端に小さいものも存在します。
小規模な銘柄は、短期で大きく値上がりする可能性がある一方で、暴落リスクやプロジェクト消滅の危険も伴います。
このため、アルトコインはハイリスク・ハイリターンな投資対象として知られているのです。
こうした多様性から、アルトコインは「ビットコインにはない革新的な機能」に魅力を感じる投資家から注目を集めてきました。
ただし、情報量が膨大で、初心者にはどこから調べればよいか難しい面もあります。
まずは市場の全体像を把握し、代表銘柄の特徴や将来性を知ることが、アルトコイン投資を始める第一歩となります。
アルトコインとビットコインの違いとは?
ビットコインは2009年に誕生した暗号資産の代表格で、時価総額や認知度で圧倒的な存在感を持ちます。
「デジタルゴールド」と呼ばれるように、資産の価値を保存する目的で保有する投資家も少なくありません。
一方、アルトコインはビットコインと仕組みが似ている部分はあっても、さまざまな用途を持つプロジェクトが含まれます。
具体例として、イーサリアムはスマートコントラクト機能を備え、分散型アプリケーションの基盤として機能します。
エックスアールピー(XRP)は国際送金に特化し、金融機関との提携により送金コストの削減を目指します。
このようにアルトコインは、技術的にも経済的にも多岐にわたる可能性を持っているのです。
ただし、ビットコインは市場支配率(ドミナンス)が比較的高く、価格推移が他の通貨に比べ安定しやすい側面があります。
アルトコインは新興プロジェクトが多く、まだ十分に検証されていない技術やビジネスモデルを試行しているケースも目立ちます。
結果として、アルトコインは急騰のチャンスがある反面、急落リスクもビットコイン以上に大きい点は意識すべきでしょう。
アルトコインと草コインの違いとは?
アルトコインはビットコイン以外の暗号資産を幅広く指す言葉ですが、その中でも特に超低時価総額で知名度が低いものを「草コイン」と呼ぶ習慣があります。
草コインは投機的要素が極めて強く、わずかな噂で価格が数倍に跳ね上がったり、その逆に一気に暴落する例もしばしば見受けられます。
草コインには、柴犬(しばいぬ)をモチーフにしたミームコインのように、ネットコミュニティの盛り上がりを頼りに成長するプロジェクトが多い印象です。
一方で、より一般的なアルトコインは、国際送金やスマートコントラクトなど、何らかの実需や技術的基盤を持っています。
投資対象として見た場合、草コインは「当たれば大きい」半面、失敗すれば価値がゼロに近づくリスクも高いです。
アルトコインの中でもメジャー銘柄は一定の流動性や活発な開発が進んでいるため、草コインよりは安定感があります。
こうした違いを理解して、自分のリスク許容度に合った銘柄を選ぶことが大切です。
アルトコインの今後はどうなる?市場動向と将来性を解説

2024年頃から、ビットコインの価格上昇を皮切りにアルトコインへも資金が流れる「アルトコインシーズン」が断続的に訪れました。
背景として、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)といった新しいブロックチェーン技術の広がりがアルトコイン需要を押し上げたことが挙げられます。
専門家の見解では、ビットコインが好調なときほどアルトコインへの資金流入も加速しやすいとされています。
ビットコインの価格が高止まりすると、投資家がより大きなリターンを狙ってアルトコインに移行する傾向があるからです。
この流れが続くと、いわゆる「アルトコインシーズン」の盛り上がりが継続すると予想されます。
一方で、米国などの規制当局がアルトコインを証券とみなす動きもあり、不透明感が残るのは事実です。
市場では、「将来性の高いプロジェクトが勝ち残り、それ以外は淘汰が進む」との見方が強まっています。
つまり、全てのアルトコインが伸びるわけではなく、投資家としては慎重な目で選定する必要があるでしょう。
2025年前後になると、Web3やメタバース、さらにAI分野との連動が進むアルトコインへの期待感が一段と高まる見通しです。
ビットコイン主導の相場でも、革新的なアルトコインは独自の材料で価格を伸ばす余地があります。
こうした状況を見極めながら、将来性のある銘柄をピックアップしておくことが重要と言えます。
今後注目の将来性のあるアルトコインランキング15選
ここでは、今後注目のアルトコインを15つ紹介していきます。
ぜひ、今後の参考にしてみてください。
1位:イーサリアム(ETH)
イーサリアムは、ビットコインに次ぐ時価総額を誇る主要アルトコインです。
スマートコントラクトという自動契約の仕組みを導入し、分散型アプリケーション(dApp)の基盤として確固たる地位を築いてきました。
DeFiやNFT分野で数多くのプロジェクトがイーサリアム上に構築され、巨大なエコシステムを形成しています。
直近では、Ethereum 2.0への移行過程でコンセンサスアルゴリズムを変更し、エネルギー消費を大幅に削減しました。
今後予定されているシャーディング技術の実装により、トランザクション処理速度の向上も期待できます。
これにより、さらに多くのアプリケーションやユーザーを呼び込み、需要拡大が見込まれるでしょう
イーサリアムは、投資家からの信頼度も高く、機関投資家が積極的に参加している点が特徴です。
長期的に見ると、ビットコインよりも多様なユースケースがあるため「成長余地が大きい」との見方が有力です。
ブロックチェーン技術の中核として、今後も業界を牽引していく可能性が高いでしょう。
もし、イーサリアム(ETH)を購入する場合はCoincheckがオススメです。
ぜひ、下記のリンクからCoincheckのサービスをチェックしてみてください。
\全取扱通貨で500円から購入可能!/
2位:エックスアールピー(XRP)
エックスアールピー(XRP)は、国際送金の効率化を目指すプロジェクト「RippleNet」の基軸通貨です。
従来の銀行間送金を大幅に高速化し、手数料を抑える仕組みを提供することで、多数の金融機関との提携を実現しています。
実際に海外送金の実需に結びついており、企業による利用が広がっています。
注目される点は、米SECとの訴訟問題が長く続いていたものの、一定の進展がみられることです。
不確実性が徐々に解消されれば、XRPが本来目指していたグローバル送金インフラとして採用される機会はさらに増えるでしょう。
銀行や決済企業がオンデマンド流動性(ODL)を活用する場面が増えれば、XRPの需要自体が伸びる見込みです。
リップルはビットコインのように「マイニング」を行わず、トランザクション処理の速さと低い手数料が特徴です。
巨大市場である国際送金分野に特化したユースケースを持ち、訴訟リスクが後退すれば一気に価格上昇が期待できるとの見方があります。
リスク要因がやや大きいものの、解消後の伸びしろには大きく期待が寄せられています。
もし、エックスアールピー(XRP)を購入する場合はGMOコインがオススメです。
ぜひ、下記のリンクからGMOコインのサービスをチェックしてみてください。
\入出金手数料が0円!/
3位:エイダコイン(ADA)
エイダコイン(ADA)は、カルダノ(Cardano)プロジェクトのネイティブトークンです。
学術的な研究成果に基づき、ブロックチェーンのセキュリティとスケーラビリティを両立するよう設計されています。
開発には専門家や研究者が多く参加し、論文ベースの厳密な検証手法を取り入れている点が特徴です。
2021年のAlonzoアップデートにより、スマートコントラクト機能を実装しました。
これをきっかけに、DeFiやNFTなど新たな分野での応用が本格化しつつあります。
さらに、ADA保有者はステーキングに参加することでネットワークの維持に貢献し、報酬を得られる仕組みが備わっています。
カルダノはコミュニティが非常に熱心で、開発ロードマップを着実に進めている印象があります。
長期視点でプロジェクトを応援する投資家が多く、価格も安定しやすい面があるでしょう。
今後も新機能の導入が予定されており、順調に進めば市場での存在感をさらに高める可能性があります。
もし、エイダコイン(ADA)を購入する場合はCoincheckがオススメです。
ぜひ、下記のリンクからCoincheckのサービスをチェックしてみてください。
\全取扱通貨で500円から購入可能!/
4位:ソラナ(SOL)
ソラナ(SOL)は、極めて高い処理速度と低コストを強みとするブロックチェーンプラットフォームです。
理論上は1秒間に数千件ものトランザクションを処理可能とされ、大量のユーザーが同時に利用しても遅延しにくい設計になっています。
こうしたスケーラビリティの高さから、NFTマーケットやDeFiプロジェクトが積極的にソラナを活用しています。
ただし、ソラナは過去にネットワーク障害を経験したことがあり、インフラの安定性に課題を抱えている面も指摘されています。
開発チームはアップグレードを繰り返し、信頼性の向上に努めている状況です。
今後は「Solana Pay」といった決済分野への展開も進めており、実社会への普及が進めばさらなる需要拡大が見込まれます。
ソラナは大型企業からの注目度も高く、エコシステムが拡大しやすい環境が整っています。
高性能なブロックチェーンを軸に、新しいサービスやdAppが続々と登場し、SOLトークンの価値向上が期待できるでしょう。
ネットワーク障害というリスクはあるものの、技術的な伸びしろが大きいプロジェクトです。
もし、ソラナ(SOL)を購入する場合はGMOコインがオススメです。
ぜひ、下記のリンクからGMOコインのサービスをチェックしてみてください。
\入出金手数料が0円!/
5位:POL(ポリゴン・旧MATIC)
ポリゴン(POL)は、イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するレイヤー2ソリューションとして誕生しました。
高速かつ低コストなトランザクションを提供するため、多くの開発者がイーサリアムの代わりにポリゴン上でDAppを構築しています。
結果として、DeFiやNFTのプロジェクトがPolygonネットワークを活用し、市場シェアを拡大してきました。
さらに、Meta社やディズニーなどの大企業と協業する事例も見られ、企業向けプラットフォームとしての信頼度も高まりつつあります。
イーサリアムが今後も主要なブロックチェーンとして発展していく中で、ポリゴンの存在意義はますます大きくなるでしょう。
L2上での取引が一般化すれば、その基盤となるMATICトークンへの需要も自然と高まることが期待されます。
技術面でも改善が続いており、さらなるブリッジやアプリケーションとの連携が進めば多くのユーザーを取り込む可能性があります。
イーサリアムの課題を補完する重要な役割を担っている点で、ポリゴンは長期的な将来性が評価される銘柄の一つです。
もし、ポリゴン(POL)を購入する場合はCoincheckがオススメです。
ぜひ、下記のリンクからCoincheckのサービスをチェックしてみてください。
\全取扱通貨で500円から購入可能!/
6位:アバランチ(AVAX)
アバランチ(AVAX)は、高速処理と低遅延を実現するスマートコントラクトプラットフォームです。
独自のコンセンサスアルゴリズムを採用し、セキュリティと拡張性を両立させています。
その結果、DeFiやNFTなどのプロジェクトが多く参入し、アバランチエコシステムが急速に拡大してきました。
さらに、中国のアリババグループやAWS(Amazon Web Services)との連携が報じられ、大手企業の注目も高まっています。
こうした企業との協業は、信頼度やブランド力を押し上げ、さらなる利用者獲得につながる可能性があります。
AVAXトークン自体はネットワーク手数料やステーキングの用途があり、プラットフォームが普及するほど価値が向上しやすい仕組みです。
アバランチは独自チェーンを複数展開できる仕組みもあり、さまざまな業界のニーズに応えられる柔軟性が魅力です。
今後はさらなるアップデートにより、高速処理を維持しつつもエコシステムが拡充される見込みです。
大手企業との連携が拡大するほど、AVAXの需要と価格も期待できるでしょう。
7位:ライトコイン(LTC)
ライトコイン(LTC)は、ビットコインに次いで歴史が古いアルトコインのひとつです。
ビットコインのコードをベースに開発されており、ブロック生成速度が速く、送金手数料が低めに設定されています。
誕生当初から「デジタルシルバー」と呼ばれ、決済手段として実用化が進むことを期待された通貨です。
2023年にはライトコインの半減期を迎え、新規発行量が減少したことで、希少価値がやや高まっています。
この仕組みにより、需給バランスの変化が価格を押し上げる要因として働く可能性があります。
ビットコイン同様に長い実稼働実績があり、ネットワークが堅牢に維持されてきた点も評価される要素です。
現在ではDeFiやNFTといった派手な用途こそありませんが、送金のしやすさや維持コストの低さを好んで使い続けるユーザーもいます。
市場全体の成長につれて、ライトコインも緩やかに価値を伸ばす余地があるでしょう。
比較的安定した歴史を持つアルトコインとして、一部の投資家から根強い支持を得ています。
8位:ポルカドット(DOT)
ポルカドット(DOT)は、ブロックチェーン同士の相互運用性を実現することを目的としたプラットフォームです。
中心となるリレーチェーンと、その周辺で独立したパラチェーンを構築する仕組みにより、複数のプロジェクトを並行して稼働させられます。
このため、Web3の中核となるインフラとして期待され、多様な分野から注目されています。
すでにDeFiやNFTなど、多くのプロジェクトがPolkadotエコシステムに参加している状況です。
パラチェーンが増え、ブロックチェーン間のクロスチェーン機能が強化されるほど、全体の利用者や開発者が増加します。
その結果、ネットワーク全体の価値が上がり、DOTトークンの需要にも反映されやすい構造です。
創設者がイーサリアムの共同創設者であることから、開発力やコミュニティの強さも高く評価されています。
将来的には、異なるブロックチェーンがシームレスに繋がり合う世界を目指しており、実現すれば大きなイノベーションとなるでしょう。
分散型インターネット(Web3)の進展に伴い、ポルカドットの役割はますます重要になりそうです。
9位:チェーンリンク(LINK)
チェーンリンク(LINK)は、ブロックチェーン上で動くスマートコントラクトに現実世界のデータを安全に取り込むためのオラクルサービスを提供しています。
この「分散型予言者機能」は、スマートコントラクトが外部情報を参照する際に不可欠な要素となります。
実際、多くのDeFiプロジェクトがチェーンリンクの価格フィードを利用しており、事実上の業界標準と認識されつつあります。
スマートコントラクトがさらに普及していくほど、信頼性の高いオラクルが必要とされるため、LINKの需要も拡大する可能性があります。
チェーンリンクは複数のブロックチェーンと連携しており、イーサリアムだけでなく他のプラットフォームでも利用が増えています。
オラクルがスマートコントラクトの「入口」として機能する以上、その重要性は今後も衰えにくいと考えられます。
こうした強固な実用性が、チェーンリンクの長期的な将来性を支える鍵になっています。
10位:ドージコイン(DOGE)
ドージコイン(DOGE)は、柴犬をマスコットにしたミームコインとして誕生しました。
もともとはジョーク的な要素が強かったものの、イーロン・マスク氏などの著名人がSNSで言及し、一時的に価格が急騰した経緯があります。
SNS主導の投機的な盛り上がりが特徴であり、他のアルトコインと異なる独特のコミュニティ文化を形成しています。
テスラ社がグッズ購入にDOGEを試験的に導入するなど、徐々に実需が生まれつつある点も注目されています。
もし本格的に大手企業が決済手段として採用すれば、コミュニティ人気との相乗効果でさらに価格が伸びる可能性があります。
ただし、開発の進捗が遅れがちで、技術的な革新が多いわけではありません。
それでもコミュニティの熱量が非常に高く、新たなアップデートや企業との連携があれば、ドージコイン独特の強気相場が再現する余地は残っています。
投資する場合はミーム的な側面を踏まえ、リスク管理をしながら楽しむ感覚も大切でしょう。
11位:シバイヌ(SHIB)
シバイヌ(SHIB)は、柴犬をモチーフにしたミームコインの一つです。
2021年には短期間で莫大な値上がりを記録し、「次のドージコイン」として注目を浴びました。
単なるジョークで終わらず、独自の分散型取引所ShibaSwapを立ち上げるなど、エコシステム拡大に意欲的な面が特徴です。
さらに、トークンを一定数焼却(バーン)する取り組みを行い、供給量を減らすことで価格安定を図る狙いも見られます。
コミュニティが非常に熱狂的で、SNSを中心に情報が拡散されやすい点が強みとなっています。
定期的に新プロジェクトを発表して話題を作り出すことで、価格が大きく動く傾向があるようです。
とはいえ、ミームコイン特有のボラティリティの高さがあるため、投資には注意が必要です。
今後の展開次第では、さらに大手取引所への上場や新サービスのリリースが期待されています。
コミュニティの盛り上がりとプロジェクトの実態をしっかり見極めながら投資判断をすることが重要です。
12位:エンジンコイン(ENJ)
エンジンコイン(ENJ)は、ブロックチェーンゲームやNFTを扱うプラットフォーム「Enjin」の基軸通貨です。
ゲーム内アイテムをNFTとして発行・管理できる仕組みを提供し、プレイヤー間で自由に売買が行えるようになります。
この技術は、既にいくつかの有名ゲームと提携し、NFT市場が拡大するほど注目度が増してきました。
メタバースやゲーム関連銘柄は近年大きな盛り上がりを見せており、ブロックチェーン技術との相性が非常に良い分野でもあります。
ENJはアイテムの裏付け資産として機能するため、利用ユーザーが増えればトークン需要が高まりやすい構造です。
また、開発チームは新機能を積極的に導入し、使いやすさを向上させる工夫を続けています。
ゲーム内で仮想通貨を使った経済圏が確立されれば、大きな市場になる可能性があります。
エンジンコインはその基盤を提供しようとするプロジェクトであり、将来的にさらに広い分野へ展開が期待されます。
NFTの普及と合わせて、ENJの価値が高まるシナリオは十分考えられるでしょう。
13位:IOST(アイオーエスティー)
IOST(アイオーエスティー)は、高速処理性能(TPS)と安価な手数料を兼ね備えたブロックチェーンを目指すプロジェクトです。
独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of Believability(PoB)」を採用し、スケーラビリティと分散性のバランスを追求しています。
こうした技術的特徴から、多数のDAppの展開を想定して開発が進められています。
日本国内でも比較的知名度が高く、2021年頃に主要取引所へ続々と上場したことで一時的に注目を集めました。
まだ大手アルトコインほどの市場規模はないものの、処理性能の高さと手数料の安さは魅力的と評価されています。
もし今後、ゲームやNFTなどのアプリケーションがIOST上に集まれば、需要は一気に拡大するかもしれません。
また、他企業との提携やDAppエコシステムの充実が進むほど、ネットワーク全体の価値は高まります。
競合プロジェクトは多いですが、IOSTの独自技術が認められれば差別化につながるでしょう。
長期的な視点で技術開発をウォッチし、展開を見極める投資家も少なくありません。
14位:ザ・サンドボックス(SAND)
ザ・サンドボックス(SAND)は、ブロックチェーン技術を活用したメタバース(仮想空間)ゲームです。
ユーザーは仮想空間内の土地やアイテムをNFTとして所有し、売買できます。
すでに大手企業や著名人がSandbox上の土地を購入しており、メタバースの可能性を象徴するプロジェクトとして注目されています。
メタバース市場は今後拡大が見込まれており、各社がゲームやイベント、バーチャルオフィスなど多彩な取り組みを展開しています。
SANDトークンは、この仮想世界での経済活動を支える基軸通貨として機能します。
利用者が増えればトークンの需要も上がり、価格上昇に寄与する可能性があります。
ただし、メタバースブームに乗って急騰した後、落ち着きを取り戻す局面もありました。
長期的に安定成長するには、継続的なコンテンツやイベント提供が不可欠でしょう。
ブロックチェーンゲームの一つの成功例として、今後も新しい展開があるか注目が集まっています。
15位:ステラルーメン(XLM)
ステラルーメン(XLM)は、個人間送金や国際決済に特化したブロックチェーンを提供するプロジェクトです。
エックスアールピー(XRP)と似たコンセプトを持ち、低コストかつ高速な送金を実現しようとしています。
法定通貨をトークン化して、手軽に送金できる仕組みが整備されている点も特徴です。
近年、中央銀行デジタル通貨(CBDC)や国際送金市場へのブロックチェーン活用が話題になる中、ステラの技術が注目を集める場面もあります。
実際に金融機関との連携やユースケース開拓が進めば、XLMの需要拡大が見込まれるでしょう。
国際協力機関との取り組みも報じられるなど、社会インフラとしてのポテンシャルを評価する意見もあります。
とはいえ、競合するプロジェクトも多いため、独自の強みをいかに発揮できるかが将来性の鍵になりそうです。
ステラルーメンは手数料の安さと高速性に着目するユーザーや企業から支持を得ており、今後の採用事例が増えれば価格上昇につながる可能性があります。
今後有望なアルトコインの選ぶポイント
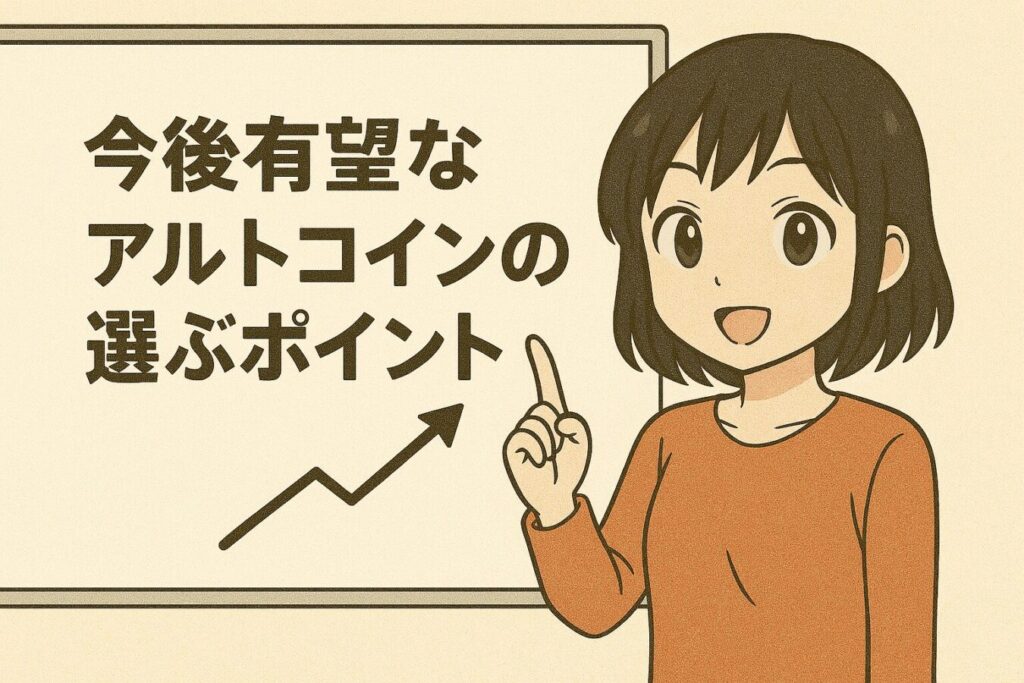
アルトコインは数が多く、それぞれ特徴やリスクが異なります。
有望な銘柄を見極めるには、以下のようなポイントを総合的にチェックするとよいでしょう。
革新的な技術や用途を持ち他にない強みがある
アルトコインの将来性を左右する大きな要因は、革新的な技術や明確な用途を持っているかどうかです。
例えば、新しいコンセンサスアルゴリズムで高速化やセキュリティ強化を実現しているプロジェクトは、他とは一線を画す可能性があります。
国際送金やスマートコントラクトなど、既存の業界課題を解決し得る銘柄は需要が伸びやすいでしょう。
「何がユニークなのか」を理解することで、そのアルトコインが長期的に注目されるかを判断できます。
単なる宣伝文句ではなく、実際に活用事例が増えているかもチェックすると信頼度が高まります。
コミュニティが活発で取引量も多い
コミュニティの活発度や取引量の多さは、プロジェクトが健全に成長している証拠と言えます。
ユーザーや投資家が積極的に意見交換を行い、イベントやアップデート情報が頻繁に共有されている通貨は、信頼度が高まりやすいです。
また、取引量(流動性)が十分にあると、相場の急激な変動が起きにくく、売買がしやすいメリットがあります。
逆に取引量が極端に少ない銘柄は、価格操作されやすく、急落時に損切りできないリスクも生じます。
コミュニティと流動性は、アルトコインを長く運用するうえで重要なチェックポイントになります。
著名な人物や企業から注目を集めている
アルトコインが世間から注目を集めるきっかけの一つに、著名人や大手企業の支持や提携があります。
例えば、イーロン・マスク氏がSNSでドージコインをたびたび話題にしたことで、価格が大きく動いた事例は有名です。
また、技術力のあるプロジェクトであれば、大企業がパートナーとして参入し、実ビジネスの拡大につなげるケースも考えられます。
こうした動きは信頼性や話題性を高め、投資家心理をプラスに働かせることが多いです。
大手企業との提携発表などは、短期的に価格を大きく押し上げる要因となるため、日々のニュースをチェックする価値があります。
開発チームが優秀でロードマップが順調に進んでいる
優秀な開発チームと明確なロードマップの存在は、アルトコインの価値を長期的に支える要素です。
ホワイトペーパーで掲げた目標をきちんと達成し、アップデートを継続しているかどうかを確認しましょう。
特に、研究者や有名企業のエンジニアが参加している場合は、技術力への期待が高まります。
定期的に新機能の実装や改善が行われている銘柄は、将来的にも発展し続ける可能性が高いです。
逆に、開発の停滞やロードマップの頓挫が見られるプロジェクトは、価格も下落しがちです。
開発状況をウォッチし、長期的な視点で判断することが失敗を減らす鍵となります。
アルトコインを購入するのにおすすめな仮想通貨取引所
日本国内でアルトコインを購入する際に取扱銘柄数が多く、初心者でも使いやすい取引所をいくつか紹介します。
セキュリティや手数料、サポート体制などを比較し、自分に合う取引所を選びましょう。
取引所を選ぶ際には、まず「取り扱い通貨の豊富さ」を確認します。
特にマイナーなアルトコインを狙いたいなら、取扱銘柄が多いサービスがおすすめです。
また、販売所方式だけでなく、板取引方式で手数料を抑えつつ売買できるかも重要なポイントとなります。
初心者はスマホアプリの使いやすさや日本語対応の充実度も無視できません。
アプリの操作が分かりにくいと、思わぬミスをしやすくなります。
セキュリティ面では、二段階認証やコールドウォレット管理などの対策が整備されているかをチェックしましょう。
Coincheck(コインチェック)

Coincheck(コインチェック)は、国内でも屈指の取扱通貨数を誇る人気取引所です。
ビットコインだけでなく、イーサリアムやリップルなど主要アルトコインのラインナップが豊富で、これから投資を始める方にとって選択肢が多いのが魅力といえます。
初心者でも操作しやすいスマホアプリが提供されており、売買の流れが直感的に把握しやすいところも特徴です。
また、積立サービスを利用すれば、自動的に定額購入することで価格変動リスクを分散することも可能です。
アルトコインの売買を一本化したい方や、まずは有名どころの銘柄を押さえておきたい初心者にとって、使い勝手の良いプラットフォームです。
\全取扱通貨で500円から購入可能!/
Bitpoint(ビットポイント)

Bitpoint(ビットポイント)は、約30種類もの暗号資産を取り扱う国内取引所です。
取引手数料が無料という点が大きな特徴で、小額からさまざまなアルトコインにチャレンジしたい人に適しています。
独自スマホアプリ「BITPOINT Lite」は、レートやチャートをリアルタイムで確認しやすく、初心者にも使いやすい設計です。
また、東証プライム上場企業グループの一員として運営されており、資本力や信頼性の面でも一定の評価があります。
時期によってはキャンペーンを実施しており、キャッシュバックや特典が得られることもあります。
購入候補のアルトコインがBitpointで取り扱われているなら、コストを抑えて取引できる選択肢として検討するのも良いでしょう。
ただし、取り扱い銘柄が他社と微妙に異なるため、事前に自分が買いたい通貨があるか確認しておくことが大切です。
\ステーキング報酬の年率国内No.1/
GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する取引所です。
大手企業グループの傘下という安心感があり、セキュリティ対策やサポート体制も充実しています。
ビットコインだけでなく、イーサリアムやリップルなど主要アルトコインの取扱数も多く、初心者から上級者まで幅広い層にオススメです。
現物取引のほかに、積立サービスやレンディングサービスなど多彩な商品が用意されている点も魅力です。
取引手数料や出金手数料も比較的安価な設定で、コストを抑えながら投資を続けられます。
操作マニュアルや学習コンテンツが充実しており、これから始める方でもスムーズに取引を覚えやすいでしょう。
複数の銘柄を分散して購入したい方や、継続的に積立投資を検討している方に特におすすめできるサービスです。
\入出金手数料が0円!/
アルトコインの今後についてまとめ
アルトコイン市場はビットコインとは異なる角度から進化を続けており、今後も大きな可能性を秘めています。
NFTやDeFi、メタバースなど新技術と結びつく場面が増え、有望な銘柄に投資すれば高いリターンを期待できるでしょう。
しかし、リスクと隣り合わせであり、プロジェクトの淘汰も進むため、慎重な銘柄選びが求められます。
- アルトコインは多様な用途や技術を持ち、ビットコインにはない革新的な機能を持つものが多い
- 将来性を見極めるには、技術的優位性、コミュニティの活発さ、企業との提携、開発の継続性などを確認すべき
- 投資の際は金融庁に登録された国内取引所を選び、セキュリティや使いやすさ、手数料を比較することが重要
- 高いリターンが期待できる反面、価格変動リスクも大きいため、無理のない範囲での投資を心がける
本記事で紹介したランキングや選び方のポイントを参考に、自分に合ったアルトコインを検討してみてください。
取引所の選定も大切で、セキュリティや手数料、サポートなどを比較しながら安全に取引を行うことが重要です。
リスク管理を徹底し、無理のない範囲で資産を運用することで、将来の資産形成に役立てられる可能性があります。
あくまで未来予測に「絶対」はありませんが、成長が期待されるテクノロジーやコミュニティに注目してみる価値は大いにあります。
本記事をきっかけに、ぜひアルトコイン投資への理解を深めていただければ幸いです。