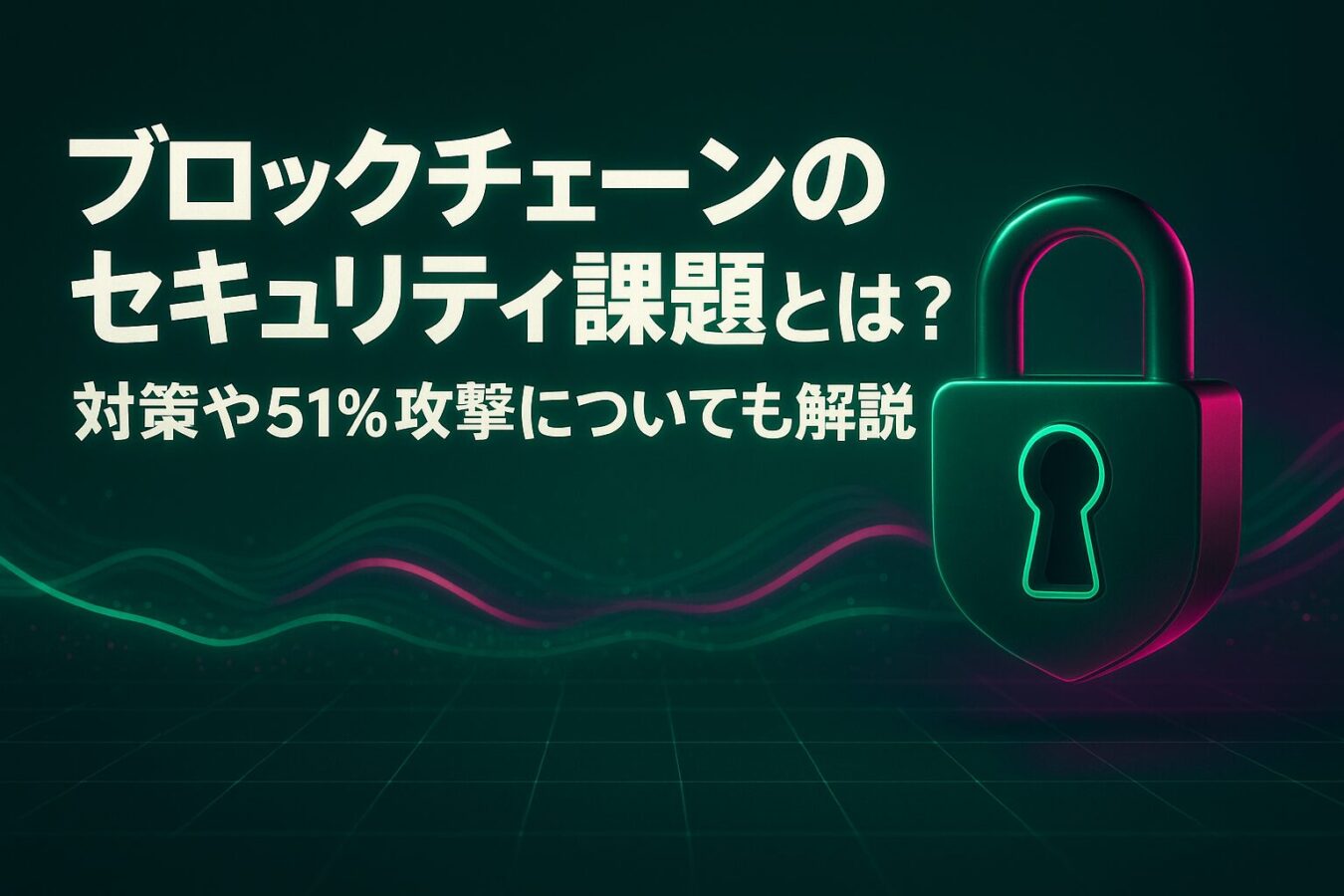自社サービスにブロックチェーン技術を導入したいけれど、セキュリティリスクが懸念で行き詰っていませんか?
51%攻撃やスマートコントラクトの脆弱性といった言葉は耳にするものの、具体的な対策や最新動向まで把握しきれていない、という技術責任者の方も多いのではないでしょうか。
特に近年、国内外でハッキングによる被害額が増加しており、対策は急務です。
今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンのセキュリティについて以下の内容について紹介してます。
- ブロックチェーンセキュリティの基本と最新の脅威動向
- 51%攻撃やスマートコントラクト脆弱性などの具体的リスクと過去の被害事例
- 実践的なセキュリティ対策、キーマネジメント、国際規格・国内ガイドライン
- ゼロ知識証明やポスト量子暗号といった先端技術の動向
- セキュリティ監査サービスの選び方と費用相場(サービス比較表あり)
- 導入検討に役立つチェックリストや専門家の体験談
ぜひ最後までご覧ください。
ブロックチェーンのセキュリティに関する用語解説
ブロックチェーンセキュリティを理解する上で、まず基本的な用語と信頼モデルを押さえておくことが不可欠です。
台帳(Ledger)、暗号技術、ノード(Node)、スマートコントラクト(Smart Contract)、信頼モデル(Trust Model)といった要素が相互に作用し、ブロックチェーンシステム全体のセキュリティレベルを形成します。
- 台帳(Ledger):取引記録をブロックという単位でまとめ、時系列に鎖(チェーン)のように繋げて記録・共有するデータベースです。分散型台帳(Distributed Ledger Technology, DLT)とも呼ばれ、多数の参加者(ノード)が同じ台帳を共有します。
- 暗号技術(Cryptography):ブロックチェーンの根幹を支える技術で、ハッシュ関数、公開鍵暗号、デジタル署名などが利用されます。ハッシュ関数はデータの改ざん検知に、公開鍵暗号とデジタル署名は取引の正当性検証や否認防止に用いられます。これによって、データの完全性と信頼性が担保されます。
- ノード(Node):ブロックチェーンネットワークに参加するコンピュータやサーバーです。各ノードは台帳のコピーを保持し、新しい取引の検証やブロックの生成・承認に関与します。ノードの分散性が、単一障害点(SPOF)のないシステムを実現します。
- スマートコントラクト(Smart Contract):あらかじめ設定されたルールに従い、契約の条件確認から実行までを自動的に処理するプログラムです。ブロックチェーン上に記録されるため、透明性が高く改ざんが困難ですが、コードに脆弱性があると攻撃の対象となります。
- 信頼モデル(Trust Model):ブロックチェーンは「トラストレス(信頼のいらない)」取引を実現すると言われます。これは特定の仲介者を信頼する必要がないという意味です。信頼は、プロトコル(合意形成アルゴリズムなど)や暗号技術、多数の分散されたノードによって担保されます。しかし、ソフトウェアのバグや人的ミス、51%攻撃など、信頼を揺るがすリスクも存在します。
ブロックチェーンのセキュリティが高いといわれている理由は?
ブロックチェーンのセキュリティは、「暗号化技術」「分散化アーキテクチャ」「コンセンサスメカニズム」という3つの柱によって支えられています。
これらがどのように連携し、システムの安全性を高めているのかを理解することが重要です。
暗号化技術とゼロトラストアーキテクチャ
ブロックチェーンにおける暗号化技術は、データの完全性、機密性、取引の正当性を保証する上で中心的な役割を果たします。
ハッシュ関数、公開鍵暗号方式、TLS/SSL運用といった要素を組み合わせることで、ネットワーク参加者同士が互いを信頼できない環境下でも正しい取引を実現します。
ハッシュ関数は任意長のデータから固定長のハッシュ値を生成する機能を持ち、一方向性や雪崩効果によって改ざん検知を容易にします。
公開鍵暗号方式(例:楕円曲線暗号)は、秘密鍵と公開鍵のペアによって取引の署名と検証を行い、不正送金や改ざんを防ぎます。TLS/SSLを利用してノード間通信を暗号化することも重要です。
分散化・コンセンサスメカニズムのセキュリティ応用
ブロックチェーンの分散化されたアーキテクチャと、コンセンサスメカニズム(PoWやPoS、BFT系など)は、攻撃を困難にする経済的・技術的な障壁を築き上げます。
分散化では、データが多数のノードに複製されるため、単一ノードが攻撃されても全体への影響は限定的です。コンセンサスメカニズムでは、正当なブロックを合意形成するプロトコルを定義し、悪意ある参加者が不正なブロックを承認させるコストやリスクを大きくします。
ビットコインのPoWでは莫大な計算資源が必要になり、イーサリアムのPoSでは不正行為に対してステークを没収するスラッシング機能などが働きます。
ブロックチェーンセキュリティのリスクシナリオ3選
ブロックチェーン技術は高いセキュリティを誇りますが、完全ではありません。
具体的なリスクシナリオとして、51%攻撃やDDoS攻撃、スマートコントラクト脆弱性、秘密鍵の流出などが挙げられます。
51%攻撃・DDoS等ネットワーク層リスク
51%攻撃のシナリオでは、悪意あるグループがネットワーク全体の計算能力やステークの51%以上を支配します。
これによって、不正な取引履歴を承認したり、正当な取引を覆したり、二重支払いを行うことが可能になります。
小規模なチェーンほど攻撃コストが低くなるため、狙われやすい傾向があります。
DDoS攻撃は多数のコンピュータから大量の処理要求を送りつけ、ノードや関連サービスを利用不能にするリスクです。
直接資金を盗む手口ではありませんが、サービス停止による機会損失や信頼低下は大きな問題になります。ネットワーク分散化と監視体制強化が対策の鍵です。
スマートコントラクト脆弱性・秘密鍵流出リスク
スマートコントラクトには、リエントランシー攻撃や整数オーバーフローなどのコード脆弱性が潜む可能性があります。
一度デプロイすると修正が難しく、大規模な資金流出に直結するケースが多々あります。
秘密鍵流出リスクでは、フィッシングやマルウェア、物理的な盗難などの手口によって不正アクセスが可能となり、大量の暗号資産が一瞬で消失する恐れがあります。
これらのリスク対策としては、スマートコントラクトのコード監査やセキュアコーディング、ハードウェアウォレットやマルチシグの活用、従業員教育が不可欠です。
ブロックチェーン業界でのハッキング事件事例
ブロックチェーン業界では、多くのハッキング事件が発生しており、その被害額も年々増加しています。
過去の事例を振り返ることで、どのようなリスクがあるかを学び、事前対策の重要性を再認識できます。
国内外主要ハッキング事件年表
以下は過去に発生した主要事件と被害額の一覧です。
特に近年はDeFiやクロスチェーンブリッジが攻撃対象となり、大きな被害額が報告されています。
| 発生年 | 事件名/対象 | 被害額(推定) | 主な原因/手口 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | Mt.Gox(日本) | 約470億円(当時のレートで約4.9億ドル) | 秘密鍵の不正アクセス、取引システムの脆弱性 |
| 2016年 | The DAO (Ethereum) | 約50億円(当時のレートで約5000万ドル) | スマートコントラクトのリエントランシー脆弱性 |
| 2018年 | Coincheck(日本) | 約580億円 | ホットウォレットの秘密鍵管理不備 |
| 2019年 | Binance | 約45億円(当時のレートで約4000万ドル) | フィッシング、APIキー不正取得 |
| 2020年 | KuCoin | 約300億円(当時のレートで約2.8億ドル) | ホットウォレットの秘密鍵流出 |
| 2021年 | Poly Network | 約670億円(当時のレートで約6.1億ドル) | クロスチェーンプロトコルの脆弱性 |
| 2022年 | Ronin Network (Axie Infinity) | 約770億円(当時のレートで約6.25億ドル) | バリデーターノードの秘密鍵侵害(ソーシャルエンジニアリング) |
| 2022年 | Wormhole | 約380億円(当時のレートで約3.26億ドル) | スマートコントラクトの署名検証ロジックの脆弱性 |
| 2023年 | Euler Finance | 約260億円(当時のレートで約1.97億ドル) | フラッシュローンを利用したスマートコントラクトのロジック欠陥 |
| 2024年 | DMMビットコイン(日本) | 約482億円(約3.05億ドル) | 秘密鍵管理インフラの脆弱性(不正アクセス) |
| 2024年 | WazirX(インド) | 約350億円(約2.35億ドル) | 多署名ウォレットの不正改ざん |
被害額は年々増加傾向にあり、攻撃手口も巧妙化しています。特にDeFiやクロスチェーン技術を狙った事例が多く報告されています。
大規模な被害が発生した事例の多くは、秘密鍵管理の不備やスマートコントラクトの脆弱性など基本的なセキュリティ対策の不足に起因しています。
秘密鍵管理では、マルチシグネチャの導入、コールドウォレットの活用、厳格なアクセス制御などが重要です。
スマートコントラクト脆弱性では、開発時のセキュアコーディング、複数のセキュリティ企業によるコード監査や形式検証、バグバウンティプログラムの実施が有効とされています。
さらに、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)の設置やインシデント対応体制の強化によって被害の最小化を図ることが大切です。
ブロックチェーンのセキュリティ性を高めるには?
ブロックチェーンシステムやスマートコントラクトの安全性を確保するには、開発段階から運用段階までの継続的なセキュリティ診断と監査が不可欠です。
ある企業のCTOは、「DeFiサービスをローンチする際、外部の専門機関によるペネトレーションテストと複数回のスマートコントラクト監査は必須プロセスでした。
初期費用はかかりますが、大規模インシデントによる損失と信頼失墜を考えれば不可欠な投資です。
ブロックチェーン特有の攻撃シナリオを理解しているテスターを見つけることが重要でした」と述べています。
ブロックチェーン セキュリティ診断とペネテスト実践手順
ペネトレーションテスト(侵入テスト)では、実際にシステムへ攻撃を試み、潜在的な脆弱性を発見して影響度を評価します。
ブロックチェーン特有の視点としては、ノード設定やコンセンサスアルゴリズム、スマートコントラクト、鍵管理システムなど幅広い領域が対象です。
テストの一般的な流れは以下のとおりです。
- 計画と準備: テスト範囲や目的を明確化し、ステージング環境を準備。
- 情報収集と分析: オープンソース情報やネットワーク構成、ソースコードなどの事前調査。
- 脆弱性スキャンと手動検証: 自動ツールによるスキャンと、手動での詳細チェックを組み合わせる。
- 攻撃試行とエクスプロイト: 発見された脆弱性を実際に利用可能か検証し、被害シナリオを評価。
- 結果分析と報告書作成: 脆弱性の深刻度評価と再現手順、修正提案をまとめる。
- 修正確認と再テスト: 報告された問題点を修正し、再度テストを実施。
監査フレームワークと継続的モニタリング対策
一度の監査で終わりではなく、継続的にセキュリティ状態を監視し、脆弱性が新たに発見されれば迅速に対処する体制が必要です。
代表的な監査フレームワークとして、SOC 2やISO/IEC 27001、CryptoCurrency Security Standard (CCSS) などが挙げられます。
OWASP Smart Contract Top 10なども、スマートコントラクト特有のリスクを把握する上で有用です。
自動監査ツールやオンチェーン監視ツールを活用し、開発から運用までDevSecOpsを徹底することが推奨されます。
Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから
⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード
ブロックチェーンのセキュリティで重要な秘密鍵の管理方法
秘密鍵の管理は、ブロックチェーンのセキュリティにおいて最重要課題の一つです。
適切なキーマネジメント戦略がなければ、大量の資産が一瞬で流出するリスクがあります。
ハードウェアウォレット導入の技術要件
ハードウェアウォレットは、秘密鍵をオフライン環境で保管し、トランザクション署名もデバイス内部で行うことでオンライン攻撃から守る仕組みです。
HSM(Hardware Security Module)など、耐タンパー性を備えた専用ハードウェアを利用するケースもあります。
HSMではFIPS 140-2/3といったセキュリティ認証を満たす製品が多く、鍵生成から破棄までのライフサイクルを安全に管理します。
費用は数十万円~数百万円と高額になる場合がありますが、多額の資産を扱う場合は有力な選択肢です。
マルチシグとしきい値署名の実装例
マルチシグ(Multi-Signature)では、複数の秘密鍵の署名がそろわなければ取引が承認されない仕組みを採用します。
例えば「2-of-3マルチシグ」なら、3つの秘密鍵のうち2つが署名しないと送金できません。単一の鍵流出では資産が奪われないため、リスク分散につながります。
一方、しきい値署名(TSS)では、複数の参加者が鍵の断片を持ち合い、協調して単一の署名を生成します。
オンチェーン上は通常の単一署名と同じ扱いなので、ガスコストなどの面で有利なケースがあります。
ブロックチェーンのセキュリティに関する規制や法律の動向
ブロックチェーン技術が社会実装されるに伴い、各国で規制や標準化が進んでいます。法的な遵守とセキュリティ基準の両立が求められ、企業にとっては重要なテーマとなっています。
ISO/IEC 23837他 国際標準の要点
ISO/IECはブロックチェーン技術に関する専門委員会を設け、用語定義やセキュリティリスク、プライバシー保護など多岐にわたる規格を策定中です。
ISO 23837では、デジタル資産カストディサービスのセキュリティ管理要件を定め、秘密鍵管理やインシデント対応、物理的セキュリティなどのチェック項目を提示しています。
国内規制・金融庁ガイドライン最新動向
日本では金融庁が暗号資産交換業者を資金決済法に基づき監督しています。
JVCEA(日本暗号資産取引業協会)の自主規制規則では、システムリスク管理や秘密鍵管理の厳格化、マネロン対策などが詳細に定められており、会員各社はこれを遵守する義務があります。
また、セキュリティトークン(STO)は金融商品取引法の対象となるため、証券扱いとして厳格なルールが適用されます。
金融庁の事務ガイドラインにもシステムリスク管理体制の評価項目が示されており、必要に応じて立入検査やモニタリングが行われます。
ブロックチェーンのセキュリティに関する最新の技術動向
ブロックチェーンセキュリティは急速に進化しており、プライバシーとスケーラビリティ、将来的な量子コンピュータへの耐性などを目的とした新技術が注目されています。
ゼロ知識証明の応用事例と課題
ゼロ知識証明(ZKP)は、秘密の情報を明かさずに「ある命題が真である」ことを証明する暗号技術です。zk-SNARKsやzk-STARKsなどの方式があり、プライバシー保護コイン(Zcashなど)やzk-Rollupsによるレイヤー2スケーリング、ID認証・資格証明などに応用されています。
ただし、証明生成時間や証明サイズ、開発の複雑性などの課題があり、標準化や相互運用性の確立はまだ途上です。
ポスト量子暗号対応ロードマップ
量子コンピュータが実用化すると、現在主流のRSAや楕円曲線暗号が破られる恐れがあります。
ポスト量子暗号(PQC)への移行は、ブロックチェーンにおいても避けて通れない課題です。
NISTはCRYSTALS-KyberやCRYSTALS-Dilithiumなどを含むPQCアルゴリズムの標準化を進めています。
既存のブロックチェーンに適用するには、鍵サイズや署名サイズの増大、計算コストの増加、オンチェーンデータ量の増大などの問題を考慮する必要があります。
クリプトアジリティを高め、暗号アルゴリズムを柔軟に切り替えられる設計が求められます。
ブロックチェーンのセキュリティ専門企業・監査サービス
スマートコントラクトやブロックチェーンプロトコルの監査を専門とする企業が増えており、それぞれ強みやサービス内容、料金体系が異なります。監査の質と実績を見極めて選ぶことが重要です。
国内外主要セキュリティ企業のサービス比較表
以下は代表的な監査企業の一覧です。監査範囲、手法、価格、納期などを比較検討し、プロジェクトに適したパートナーを選定する必要があります。
| 企業名 | 主な拠点 | 強み・特徴 | 主な監査対象 | 料金目安 | 納期目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| CertiK | 米国 | 形式検証、自動監査ツール(Skynet)、総合評価、保険商品との連携 | スマートコントラクト、プロトコル、ウォレット | 要問い合せ | 要問い合せ |
| Trail of Bits | 米国 | 高度なセキュリティリサーチ、カスタムツール開発 | 複雑なコントラクト、ブロックチェーン基盤、暗号プロトコル | 要問い合せ | 要問い合せ |
| Quantstamp | 米国 | 自動スキャン+手動監査、DeFi案件多数 | スマートコントラクト、ネットワーク | 要問い合せ | 要問い合せ |
| PeckShield | 中国・米国 | インシデント対応、リアルタイム脅威検知、DeFiに強み | スマートコントラクト、DApps、取引所 | 要問い合せ | 要問い合せ |
| OpenZeppelin | 米国 | Solidityライブラリ(Contracts)開発元 | スマートコントラクト(ERC標準) | 要問い合せ | 要問い合せ |
| ConsenSys Diligence | 米国 | イーサリアム専門知見、MythXツール | スマートコントラクト、DApps | 要問い合せ | 要問い合せ |
| LayerX (日本) | 日本 | 国内実績豊富、コンサルも対応 | スマートコントラクト、ブロックチェーンシステム | 要問い合せ | 要問い合せ |
| NRIセキュアテクノロジーズ (日本) | 日本 | 総合セキュリティサービス、金融知見 | スマートコントラクト、プラットフォーム | 要問い合せ | 要問い合せ |
料金や納期はあくまで目安で、コードの行数や複雑度によって変動します。
実績や専門分野、コミュニケーション品質も含め、総合的に判断すると良いでしょう。監査は単なる「お墨付き」ではなく、リスクを洗い出して対策を施すための重要なプロセスです。
ブロックチェーンのセキュリティに関するFAQ(よくある質問)
ここでは、ブロックチェーンのセキュリティについてよくある質問とその答えを紹介していきます。
ブロックチェーンのセキュリティは完全なのか?
いいえ、ブロックチェーン技術は高い堅牢性を備えていますが、51%攻撃やスマートコントラクトのバグ、秘密鍵管理の失敗など様々なリスクがあります。
人的要因や外部システムの脆弱性も含めて多層的に対策することが重要です。改ざん耐性が高いからといって絶対的な安全を保証するものではありません。
51%攻撃を防ぐ具体策は何か?
PoWチェーンの場合はハッシュレートの分散やアルゴリズムの選定、PoSチェーンの場合はステークの分散やスラッシング導入、チェックポイント方式などが挙げられます。
ネットワーク監視の強化や異常検知も含め、攻撃コストを高める仕組みを多面的に構築することが鍵です。
スマートコントラクト診断費用はいくらか?
プロジェクトの規模や複雑度、コード行数、依頼先の企業によって大きく異なりますが、小規模のERC-20トークンなどで数十万円~数百万円、中規模DeFiプロジェクトで数百万円~数千万円、大規模で独自性が高い場合は数千万円以上になることもあります。
被害を防ぐ投資と捉え、早期に監査を実施することが望ましいです。
ブロックチェーン セキュリティ 応用例はどんな業界?
金融分野(国際送金、貿易金融、証券取引)、物流・サプライチェーン(トレーサビリティ、偽装防止)、ヘルスケア(電子カルテ共有、医薬品管理)、行政サービス(投票システム、公文書管理)など、多様な業界で利用が検討されています。いずれも高いデータ信頼性を求められる領域です。
ブロックチェーンのセキュリティについてまとめ
今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンのセキュリティについて以下の内容について紹介してきました。
ブロックチェーンセキュリティの基本概念(暗号化、分散化、コンセンサス)と重要性、主要リスク(51%攻撃、スマートコントラクト脆弱性、秘密鍵流出など)、過去事例から学ぶ教訓、ペネトレーションテスト・監査の重要性、キーマネジメント(ハードウェアウォレット・マルチシグ)、国内外の規制と国際標準、ゼロ知識証明やポスト量子暗号といった最新動向、監査サービスの選び方と費用感など、幅広いトピックを網羅しました。
ブロックチェーンの導入を検討する際は、これらのリスクと対策を十分理解し、自社に最適なセキュリティ戦略を立てることが成功への近道です。特に、スマートコントラクトの脆弱性と秘密鍵の管理は大きなリスク要因となるため、専門家の知見を積極的に活用しましょう。新技術の継続的な学習も欠かせません。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。
- Web3技術の活用方法がわからない
- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい
- NFTを活用したマーケティング施策を検討している
- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい
個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。