「NFTやブロックチェーンという言葉をよく聞くけれど、違いがよくわからない…」
「デジタル資産をビジネスに活用したいが、何から手をつければ良いか悩んでいる…」
Webマーケターや事業企画担当者として、このような課題を感じていませんか?Web3時代の新たな収益機会として注目されるNFTですが、その根幹技術であるブロックチェーンを理解しないままでは、ビジネス活用の本質を見誤る可能性があります。
今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンとNFTについて、以下の内容を徹底解説します。
- ブロックチェーンとNFTの基本的な定義と仕組み
- 両者の明確な違いと、切っても切れない関係性
この記事を最後まで読めば、ブロックチェーンとNFTの基礎知識はもちろん、ビジネス活用の具体的なイメージを掴み、社内での企画提案に役立つヒントが得られます。ぜひ、最後までご覧ください。
“ブロックチェーン”と”NFT”とは?基本からわかりやすく解説
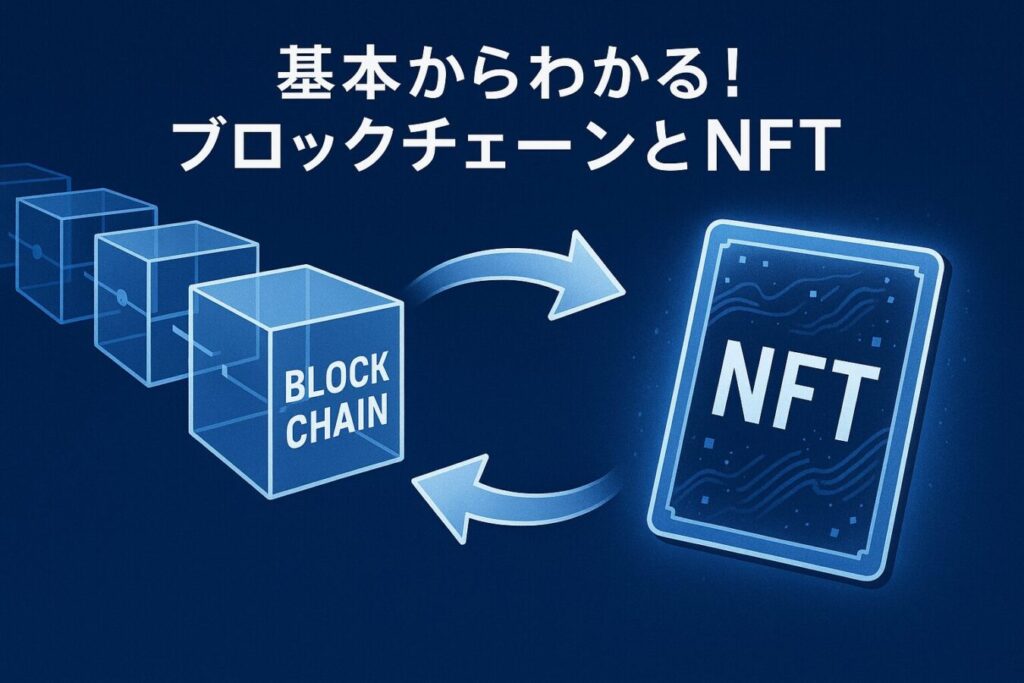
はじめに、ブロックチェーンとNFTがそれぞれ何を指すのか、その基本的な概念を解説します。両者の関係性にも触れながら、初心者にも分かりやすく説明します。
ブロックチェーンとは?取引を安全につなぐ技術の仕組み
ブロックチェーンとは、一言でいえば「取引履歴を暗号技術によって鎖(チェーン)のようにつなぎ、複数のコンピューターに分散して記録・管理する技術」です。日本語では「分散型台帳技術」とも呼ばれます。
この技術には、主に3つの大きな特徴があります。
- 分散管理によるゼロダウンタイム: 特定の中央管理者が存在せず、P2P(ピアツーピア)ネットワークに参加する多数のコンピューター(ノード)が同じデータを共有します。そのため、一部のコンピューターがダウンしてもシステム全体が停止することはありません。
- 改ざん耐性: 取引データは「ブロック」という単位でまとめられ、暗号技術(ハッシュ関数)を用いて時系列順に連結されます。一度記録された情報を改ざんするには、それ以降の全てのブロックを書き換える必要があり、さらにネットワークの多数の合意(コンセンサスアルゴリズム)を得る必要があるため、改ざんは極めて困難です。
- 透明性: 取引の記録はネットワーク参加者に対して公開されており(プライベート型を除く)、誰でもその履歴を検証できます。この透明性が、取引の信頼性を担保します。
この「安全にデータを記録し、改ざんが非常に難しい」という仕組みが、後述するNFTの価値を支える土台となっています。
NFT(非代替性トークン)とは?デジタルデータに唯一無二の価値を与える仕組み
NFTは「Non-Fungible Token(ノン-ファンジブル・トークン)」の略で、日本語では「非代替性トークン」と訳されます。
「非代替性」とは、「替えが効かない、唯一無二である」という意味です。例えば、あなたが持っている1万円札は、友人が持っている1万円札と交換しても価値は変わりません。これは「代替可能」です。しかし、有名な画家が描いた一点物のアート作品は、他の作品と交換することはできません。これが「非代替性」です。
これまで、デジタルデータ(画像、動画、音楽など)は簡単にコピー・複製が可能で、どれが「本物」でどれが「コピー」なのかを区別できませんでした。そのため、デジタルデータに資産価値を持たせることは困難でした。
NFTは、この課題をブロックチェーン技術によって解決します。デジタルデータに「これは唯一無二のオリジナルである」という証明書(鑑定書・所有証明書)を紐付け、その情報をブロックチェーン上に記録するのです。これにより、デジタルデータに唯一無二の価値と所有権を付与することができます。
“ブロックチェーン”と”NFT”の違いと関係性は?

ブロックチェーンとNFTは密接な関係にありますが、その役割は全く異なります。ここでは、両者の違いと比較、そして「なぜセットで語られるのか」という関係性について解説します。
一目でわかる!ブロックチェーンとNFTの違いを比較表で解説
両者の違いを理解するために、以下の比較表をご覧ください。ビジネスパーソンがポイントを掴めるよう、簡潔にまとめています。
| 比較項目 | ブロックチェーン | NFT |
|---|---|---|
| 役割 | データを記録・管理する技術基盤(インフラ) | ブロックチェーン上で発行される唯一無二のデジタル資産(データ) |
| 目的 | データの永続性、改ざん耐性、透明性を担保すること | デジタルデータの所有権を証明し、唯一性を保証すること |
| 具体例 | イーサリアム、ビットコイン、Solana、Polygon | デジタルアート、ゲームアイテム、会員権、チケット |
| 技術レイヤー | レイヤー1(土台となる技術) | レイヤー2(土台の上で機能するアプリケーション層) |
【関係性】NFTはブロックチェーンという土台の上で成り立つ資産
両者の関係性を例えるなら、ブロックチェーンが「信頼性の高い土地の登記簿データベース」で、NFTが「そのデータベースに記録された、一つ一つの土地の権利書」のようなものです。
NFTという「権利書」が存在するためには、その権利情報(誰が作成し、誰が所有しているか、いつ取引されたかなど)を、誰もが確認でき、かつ誰にも改ざんされない形で記録しておく「登記簿データベース」が不可欠です。
このデータベースの役割を果たすのが、ブロックチェーン技術です。NFTの取引履歴はすべてブロックチェーン上に刻まれます。この消せない記録があるからこそ、デジタルデータに資産としての価値が生まれ、人々は安心してNFTを売買できるのです。
つまり、NFTはブロックチェーンという土台がなければ成り立たない資産であり、両者は切っても切れない関係にあるのです。
なぜNFTにはブロックチェーンが必要なの?

デジタルデータに価値を与えるNFTですが、その価値の根源はブロックチェーン技術にあります。もしブロックチェーンがなければ、NFTはどのような課題を抱えるのでしょうか。ここでは、NFTにとってブロックチェーンがなぜ不可欠なのか、その技術的な必要性を深掘りします。
NFTの価値の源泉「唯一性」と「所有権」の証明
デジタルデータの最大の特徴であり、同時に課題でもあったのが「容易にコピー(複製)できる」という点です。右クリック一つで誰でも簡単に画像を保存できてしまいます。この性質のため、デジタルアートや音楽は、どれがオリジナルで、誰が本当の所有者なのかを証明することが困難でした。
ブロックチェーンは、この問題を解決します。NFTが発行されると、「トークンID」という個別の識別番号が割り当てられ、そのNFTの作成者、所有者、取引履歴といった情報がブロックチェーン上に記録されます。この記録は、世界中のコンピューターに分散して保存され、一度書き込まれると後から変更したり削除したりすることが極めて困難です。
この「改ざん不可能な記録」こそが、NFTに唯一無二の価値(希少性)と、明確な所有権をもたらすのです。ブロックチェーンという信頼の基盤があるからこそ、単なるデジタルデータが、価値ある資産として認められるのです。
透明性と追跡可能性(トレーサビリティ)の担保
ブロックチェーンのもう一つの重要な役割は、取引履歴の透明性と追跡可能性(トレーサビリティ)を確保することです。
NFTが最初に誰によって作られ(ミントされ)、その後、いつ、誰から誰へ、いくらで売買されたかという全履歴は、ブロックチェーン上で誰でも閲覧することができます。これにより、アート作品の真贋証明が容易になります。例えば、有名なデジタルアーティストが発行した本物かどうかは、そのアーティストの公式ウォレットアドレスから発行された履歴をたどることで確認できます。
この透明性は、中古市場での取引の健全性を保つ上でも極めて重要です。クリエイターは、自身の作品が二次流通(転売)されるたびに、売買代金の一部をロイヤリティとして自動的に受け取る設定も可能であり、これはブロックチェーン上のプログラム(スマートコントラクト)によって実現されます。ビジネス視点で見れば、これはクリエイターエコノミーを活性化させる画期的な仕組みと言えるでしょう。
主なブロックチェーンとNFTの種類を紹介
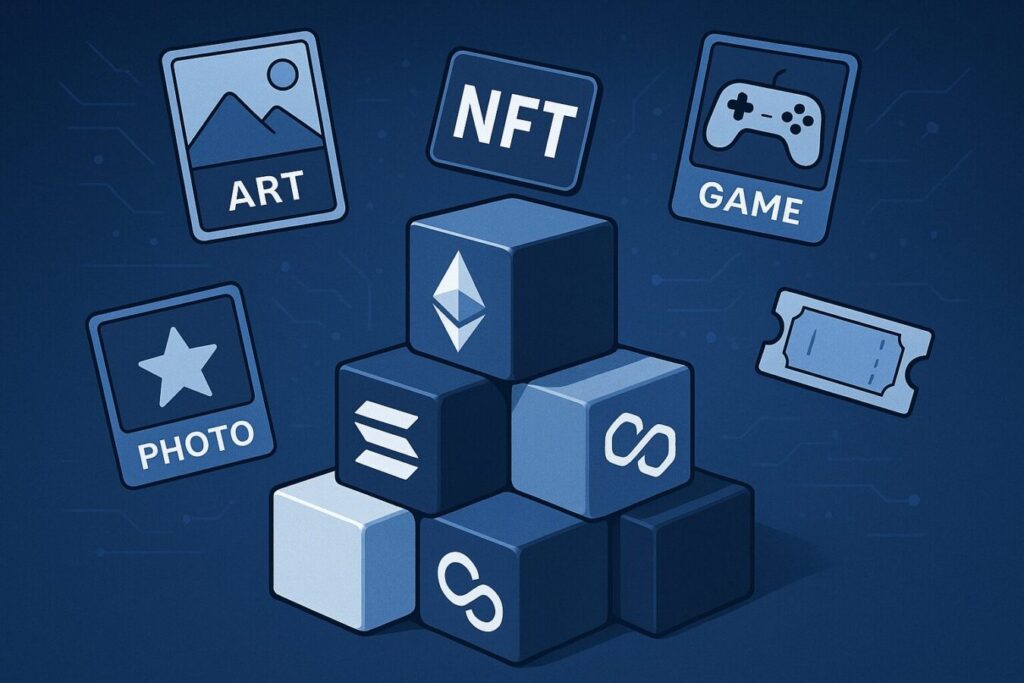
NFTは様々なブロックチェーン上で発行・取引されています。それぞれのブロックチェーンには特徴があり、目的や用途によって使い分けられます。この章では、代表的なブロックチェーン基盤と、その上で展開されるNFTのカテゴリを紹介します。
NFT開発で利用される代表的なブロックチェーンの種類と比較
NFTプロジェクトを立ち上げる際、どのブロックチェーン基盤を選ぶかは非常に重要です。
| ブロックチェーン | 特徴 | ガス代(手数料) | 処理速度 | エコシステム |
|---|---|---|---|---|
| イーサリアム (Ethereum) | 最も歴史が長く、利用者・開発者が多いNFTの代表格。信頼性が高い。 | 高い傾向にある | 比較的遅い | 最大規模。多くのツールやマーケットプレイスが存在。 |
| Polygon (ポリゴン) | イーサリアムの拡張ソリューション(レイヤー2)。互換性を持ちつつ、安価で高速。 | 非常に安い | 速い | 急成長中。多くの大手企業が採用。 |
| Solana (ソラナ) | 独自の仕組みで超高速・低コストを実現。大規模なNFT発行に向いている。 | 非常に安い | 非常に速い | ゲームやDeFiを中心に拡大。 |
| Flow (フロー) | NBA Top Shotなどを手掛けたDapper Labsが開発。エンタメ領域に特化。 | 安い | 速い | 大手ブランドとの提携が多く、初心者にも優しい。 |
活用されるNFTの種類(カテゴリ)
ブロックチェーン技術を基盤に、NFTは多様な分野で活用されています。ここでは具体的なプロジェクト名を交えながら、主要なカテゴリを紹介します。
- NFTアート: デジタルアーティストが作成した一点物のアート作品。Beeple氏の作品が高額で落札されたことで一躍有名になりました。
- ブロックチェーンゲームのアイテム: ゲーム内で使用するキャラクター、武器、土地などがNFTとして取引されます。『Axie Infinity』や『The Sandbox』などが有名で、遊んで稼ぐ(Play to Earn)モデルを生み出しました。
- メタバース上の土地・アバター: 「メタバース」の活用例として、『Decentraland』などの仮想空間内の土地や、アバターが着るファッションアイテムがNFTとして売買されています。
- 会員権・チケット: イベントの入場券や、特定のコミュニティへの参加権をNFTとして発行するケース。保有者限定の特典を提供しやすく、二次流通の管理も可能です。
- トレーディングカード: NBA Top Shotのように、スポーツ選手のプレイ動画のハイライトなどを収集・交換できるデジタルトレーディングカードも人気です。
【2025年最新】ブロックチェーンとNFTの企業活用事例5選
Webマーケターや事業企画担当者にとって、他社がどのようにNFTを活用しているかは最大の関心事でしょう。ここでは2024年以降の国内外の最新事例から、特に実用的な5つを厳選して紹介します。単なる販売で終わらない、顧客エンゲージメントや事業連携のヒントが満載です。
【国内/航空・地方創生】日本航空(JAL)× 博報堂:体験型NFT「KOKYO NFT」による関係人口創出

日本航空(JAL)と博報堂は、地域の特別な体験とデジタル資産を組み合わせた「KOKYO NFT」の実証実験を進めています。2024年には第二弾として茨城県の酒蔵と連携し、特別な日本酒の購入権や限定イベントへの参加権をNFTとして販売しました。この取り組みの狙いは、一度きりの観光客(交流人口)を、地域と継続的に関わる「関係人口」へと深化させることです。NFTを「旅の思い出」として所有してもらうだけでなく、保有者限定のコミュニティを通じて長期的な関係を築く、地方創生の新しいアプローチとして注目されています。
【国内/交通】JR北海道:記念乗車券NFTによる新たな鉄道ファン体験の創出

JR北海道は2024年から、引退車両のラストラン記念乗車券などをNFTとして発行・販売するプロジェクトを開始しました。従来の紙の記念切符とは異なり、NFTはブロックチェーン上に乗車履歴や記念品としての所有権が永続的に記録されます。
これにより、コレクション性が高まるだけでなく、偽造防止にも繋がります。鉄道ファンにとっては、思い出をデジタル空間で未来永劫保有できるという新たな価値を提供し、エンゲージメントを高める施策となっています。2025年にかけても、他社との連携を含め、さらなる展開が期待されます。
【海外/コーヒーチェーン】Starbucks:ロイヤリティプログラム「Odyssey」のWeb3展開

米国スターバックスは、既存の強力なリワードプログラムをWeb3技術で拡張した「Starbucks Odyssey」を2022年末から展開しました。(※2024年3月にベータ版は終了しましたが、Web3活用の先進事例として非常に参考になります。)
ユーザーはコーヒーに関するクイズに答えたり、店舗を訪れたりする「Journey」というクエストをクリアすると、記念NFT(Journey Stamp)を獲得。このスタンプを集めると、限定グッズとの交換や、コーヒー農園への旅行などの特別な体験への参加権が得られる仕組みでした。ゲーム性を取り入れて顧客体験を向上させ、ファンとの新たな繋がりを生み出す試みとして大きな話題を呼びました。
【海外/アパレル】adidas:NFTプロジェクト「ALTS by adidas」によるファンダム形成
adidasは、NFTプロジェクト「ALTS by adidas」を通じて、熱心なファンとの長期的なコミュニティを形成しています。このNFTを保有すると、ホルダー限定の物理的なアパレル商品や、パートナー企業が開発するメタバースゲームで使えるデジタルウェアラブルなど、様々な特典へのアクセス権が得られます。
2024年以降も継続的にホルダー向けのユーティリティ(特典)を提供しており、単発のキャンペーンで終わらせない強い意志が感じられます。ブランドの世界観を共有するファン(ファンダム)を形成し、ブランドロイヤリティを高める最先端の事例です。
【国内/チケット】楽天チケット:「NFTチケット」機能による二次流通と特典提供の実現

楽天グループは2024年、チケット販売サービスの「楽天チケット」において、チケットをNFTとして販売できる機能の提供を開始しました。この「NFTチケット」は、イベントの入場券として利用できるだけでなく、イベント後には半券が記念品として残り、コレクションできます。
さらに、公式の二次流通市場で売買することも可能です。この仕組みの画期的な点は、二次流通で売買が成立した際に、収益の一部がアーティストや主催者に還元される設定ができることです。これにより、不正な高額転売を抑制しつつ、主催者側に新たな収益機会をもたらすという、チケット業界の長年の課題を解決する可能性を秘めています。
Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから
⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード
ブロックチェーンやNFTを始めるメリットとは?

ここまで見てきたように、多くの企業がNFTビジネスに挑戦しています。では、具体的にどのようなメリットが期待できるのでしょうか。ここでは企業の視点から、「収益機会」「ブランディング」「コミュニティ」の3つの観点で、NFTに取り組む利点を解説します。
新たな収益源の確保とグローバル市場へのアクセス
最大のメリットは、新たな収益源を創出できる点です。デジタルアートやコレクティブルアイテムといった「デジタルコンテンツ販売」による一次収益はもちろん、NFTの大きな特徴である「二次流通時のロイヤリティ収入」は、継続的な収益モデルとして非常に魅力的です。
スマートコントラクトにプログラムを組むことで、作品が転売されるたびに、売上の一部が自動的にクリエイターや発行者に還元される仕組みを構築できます。また、NFTはインターネット上で国境を越えて取引されるため、最初からグローバル市場をターゲットにビジネスを展開できる可能性も秘めています。
先進的なブランドイメージの構築とPR効果
Web3やNFTは、まだ多くの企業にとって未知の領域です。そのような中で、いち早くこの分野に挑戦することは、企業が「先進的で、革新的なことに取り組んでいる」という強力なブランドイメージを社会に与えます。
新しい技術を活用した取り組みは話題性が高く、メディアに取り上げられたり、SNSで拡散されたりしやすいため、多額の広告費をかけずとも高いPR効果が期待できます。これは、特に競争の激しい業界において、他社との差別化を図る上で大きなアドバンテージとなり得ます。
顧客との新しい関係構築(ファンコミュニティの醸成)
NFTは単に商品を売って終わり、という一方通行の関係ではありません。NFTを「会員証」として活用し、保有者だけがアクセスできる限定コンテンツや特典、特別なイベントを提供することで、顧客との間に特別な繋がりを生み出すことができます。
例えば、保有者限定のオンラインコミュニティ(Discordサーバーなど)を運営すれば、企業とファン、あるいはファン同士が直接コミュニケーションをとる場が生まれます。これにより、顧客は単なる消費者から、ブランドを共に育てていく「共創者」へと変わり、熱量の高いファンコミュニティを醸成することが可能になります。
ブロックチェーンやNFTを始める前に知っておくべき注意点とリスクとは?

NFTビジネスには大きな可能性がありますが、新しい技術領域ならではの注意点やリスクも存在します。ここでは、技術的な課題から、法律、会計、セキュリティといった実務的な側面まで、ビジネスとして取り組む上で必ず押さえておくべきポイントを解説します。
技術的な課題:ガス代の高騰とスケーラビリティ問題
NFTの取引で最も広く使われているイーサリアムブロックチェーンには、以前から課題として指摘されている点があります。一つは「ガス代」と呼ばれる取引手数料です。ネットワークの利用が集中し、混雑すると、このガス代が数千円から数万円にまで高騰することがあります。
もう一つは、一度に処理できる取引の数に限りがある「スケーラビリティ問題」です。これらの課題は、ユーザー体験を損なう要因になりかねません。対策として、イーサリアムの処理を助けるPolygonのような「レイヤー2」と呼ばれる技術を活用し、ガス代を抑え、処理速度を向上させるプロジェクトが増えています。
法規制と税務・会計処理の複雑さ
NFTを取り巻く法律や税制は、まだ発展途上の段階です。NFTの所有権がどこまでの権利(例えば、著作権や商用利用権)を含むのかは、発行時の規約によって異なり、法的な解釈が定まっていない部分もあります。また、景品表示法や賭博罪など、既存の法律に抵触しないような設計も必要です。税務・会計面でも、企業がNFTを売買して得た利益の計算方法や、資産として保有する場合の評価方法など、複雑な論点が多く存在します。
2025年度の税制改正で法人保有の暗号資産に関する一部緩和がありましたが、依然として専門家への相談は不可欠です。安易な参入は思わぬ法務・税務リスクを招く可能性があるため、事前の十分な検討が求められます。
セキュリティリスク:ハッキングや詐欺(スキャム)への対策
ブロックチェーンやNFTの世界では、自己責任での資産管理が原則です。企業の公式プロジェクトを装って偽のNFTを販売する詐欺サイトや、秘密鍵(資産へのアクセスキー)を盗み出そうとするフィッシング詐欺(スキャム)が横行しています。
企業としてNFTプロジェクトを運営する場合、自社の資産を守るための厳重な秘密鍵の管理はもちろん、顧客が詐欺被害に遭わないように注意喚起を行うことも重要です。公式ウェブサイトやSNSアカウントを明確にし、安易にDM(ダイレクトメッセージ)内のリンクをクリックしないよう呼びかけるなど、利用者へのセキュリティ教育も企業の責任の一つと言えるでしょう。
ブロックチェーンがNFT以外で活用されるケース
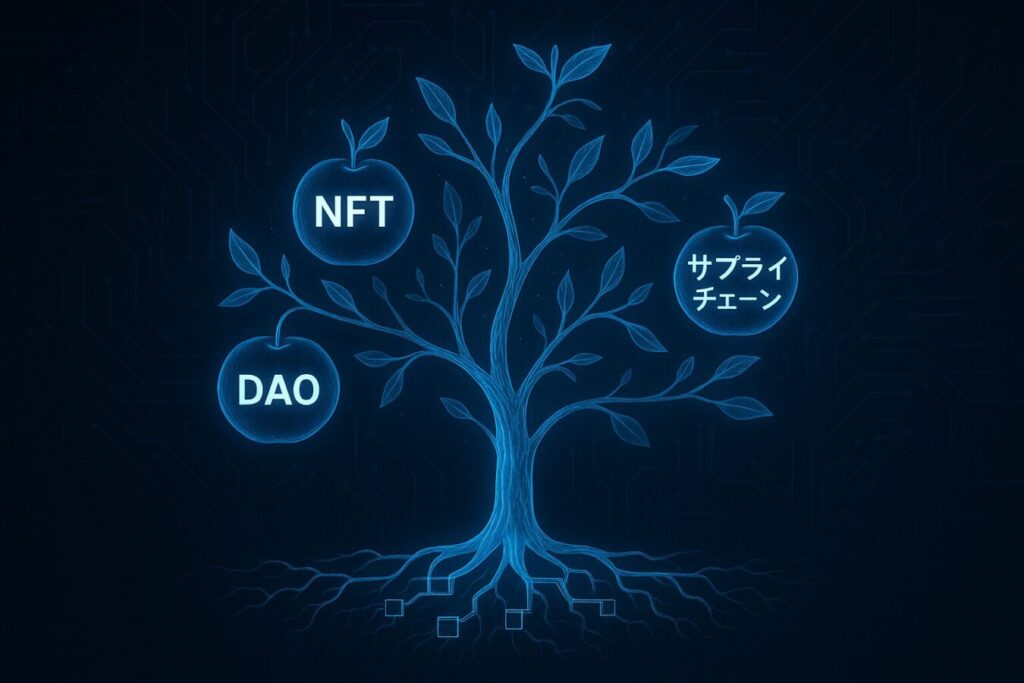
NFTはブロックチェーン技術の数ある活用事例の一つに過ぎません。その基盤技術であるブロックチェーンは、社会の様々な領域でイノベーションを起こすポテンシャルを秘めています。ここでは、NFT以外の代表的な活用ケースを3つ紹介します。
金融分野(DeFi):中央管理者を介さない金融システム
DeFi(Decentralized Finance)は「分散型金融」と訳され、ブロックチェーン上に構築された、中央集権的な管理者を必要としない金融サービスのエコシステムです。
銀行や証券会社といった従来の金融機関を介さずに、暗号資産の貸し借り(レンディング)、交換(DEX: 分散型取引所)、保険などの金融取引を、プログラム(スマートコントラクト)を通じて自動的に行うことができます。これにより、地理的な制約なく、より透明で効率的な金融サービスへのアクセスが可能になると期待されています。
サプライチェーン管理:生産・流通過程のトレーサビリティ向上
商品の生産から消費者の手元に届くまでの流通過程(サプライチェーン)において、ブロックチェーンは絶大な効果を発揮します。製品の原材料、生産地、加工日、輸送業者といった情報をブロックチェーンに記録することで、改ざん不可能な流通履歴が完成します。
消費者は、商品のQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、その商品が本物であることや、安全なルートで運ばれてきたことを確認できます。これは、高級ワインやブランド品、医薬品などの真贋証明や、食品の産地偽装防止、リコール時の迅速な追跡などに役立ちます。
ガバナンス(DAO):自律的に運営される分散型組織
DAO(Decentralized Autonomous Organization)は「分散型自律組織」と呼ばれ、特定の所有者や管理者が存在せず、参加者全員で意思決定を行う新しい組織の形です。
組織のルールはスマートコントラクトとしてコードに記述されており、運営方針の決定などは「ガバナンストークン」と呼ばれる議決権トークンを持つメンバーの投票によって行われます。プロジェクトの運営から投資ファンドまで、様々な目的のDAOが生まれており、より透明で民主的な組織運営のモデルとして注目を集めています。
ブロックチェーンとNFTの業界動向と今後の展望

ブロックチェーンとNFTの市場は、一時的なブームを経て、より実用的な活用フェーズへと移行しつつあります。ここでは、大手企業の参入動向や技術の進化を踏まえ、今後の市場の展望について考察します。
大手IT企業・有名ブランドの参入による市場拡大
2023年以降、Google、Meta、Amazonといった巨大IT企業や、Starbucks、Nike、adidasのようなグローバルブランドが、ブロックチェーンやNFTの活用を本格化させています。
例えば、Google Cloudはブロックチェーンノードのホスティングサービスを提供するなど、開発者向けのインフラ整備を進めています。大手企業が参入することで、技術の信頼性が向上し、これまでこの分野に馴染みのなかった一般層にもサービスが届きやすくなります。これにより、市場全体の信頼性が高まり、普及がさらに加速していくと考えられます。
技術の進化と「マスアダプション」への期待
市場拡大の鍵を握るのが「マスアダプション(大衆への普及)」です。現状では、ウォレットの作成やガス代の支払いなど、ユーザーがブロックチェーン技術を直接意識しなければならない場面が多く、これが普及のハードルとなっています。
しかし、ガス代問題を解決するレイヤー2技術の進化や、クレジットカードでNFTが買えるサービスの登場、ウォレットのUI/UX改善など、技術的なハードルを下げる取り組みが絶えず行われています。将来的には、ユーザーがブロックチェーンやNFTを意識することなく、その恩恵だけを享受できるサービスが主流となり、マスアダプションが一気に進むと期待されています。
ブロックチェーン・NFTに関するFAQ(よくある質問)
最後に、ブロックチェーンやNFTに関してよく寄せられる質問に、Q&A形式でお答えします。技術的な疑問からビジネス面の疑問まで、ここでスッキリ解消しましょう。
Q1. NFTの「ガス代」とは何ですか?なぜ高くなることがあるのですか?
A1. ガス代とは、ブロックチェーンネットワークを利用する際に支払う「手数料」のことです。NFTの発行や売買など、ブロックチェーンに取引を記録してもらうための作業(計算)を、ネットワークに参加するコンピューター(マイナーやバリデーター)に依頼するためのコストと考えると分かりやすいでしょう。この手数料は、ネットワークの混雑具合によって変動します。
取引したい人が殺到すると、処理の順番待ちが発生し、自分の取引を優先してもらうために、より高い手数料を支払う必要が出てきます。これが、高速道路の渋滞時に料金が高くなるのと似た仕組みで、ガス代が高騰する原因です。
Q2. コピーできるデジタルデータなのに、NFTにはなぜ価値がつくのですか?
A2. NFTの価値は、デジタルデータそのものではなく、ブロックチェーンによって証明される「所有権」にあります。誰でもレオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」の絵のポストカードを買うことはできますが、フランスのルーブル美術館が所蔵している「本物(オリジナル)」は世界に一つしかありません。
NFTもこれと同じで、たとえデータがコピーされても、ブロックチェーン上に記録された「本物の所有者である」という証明はコピーできません。この唯一無二の所有権の証明があるからこそ、デジタルデータに資産としての価値が生まれるのです。
Q3. 日本企業でブロックチェーンやNFTビジネスに成功している例はありますか?
A3. はい、多数あります。この記事でも紹介した、JALの「KOKYO NFT」による地方創生の取り組みや、JR北海道の「記念乗車券NFT」、楽天の「NFTチケット」による新たな収益モデルの構築などが代表的な成功事例です。
その他にも、ゲーム業界やアニメ・マンガ業界、ファッション業界など、様々な分野で日本企業が独自の強みを活かしたNFTプロジェクトを展開し、ファンコミュニティの形成や新たな顧客体験の創出に成功しています。
Q4. NFTアートは著作権も購入者に譲渡されるのですか?
A4. 原則として、NFTを購入しても譲渡されるのはデジタルデータの「所有権」のみであり、作品の「著作権」は制作者(クリエイター)に残ります。
ただし、これはあくまで一般論です。NFTを販売する際の利用規約によっては、著作権の一部または全部が購入者に譲渡されるケースや、商用利用が許可されるケースもあります。重要なのは、NFTを購入する前に、そのNFTにどのような権利が付与されているのか、利用規約をしっかりと確認することです。
ブロックチェーンとNFTについてまとめ
今回、Pacific Meta Magazineでは、ブロックチェーンとNFTについて以下の内容を紹介してきました。
- ブロックチェーンは「改ざん困難な取引記録のデータベース」という信頼の土台であり、NFTは「その土台の上で価値が証明された唯一無二のデジタル資産」である。
- 両者の違いは「技術基盤」と「資産」であり、NFTの価値はブロックチェーンの特性(唯一性の証明、透明性)によって支えられている。
- NFTにはアート、ゲーム、会員権など多様な種類があり、イーサリアムやPolygonなど目的に応じたブロックチェーン基盤が使われる。
- 国内外の大手企業が、顧客エンゲージメント向上や新たな収益源確保のためにNFT活用を進めている。
- ビジネスとして導入するメリットは大きいが、ガス代、法規制、セキュリティなどのリスクも十分に理解する必要がある。
ブロックチェーンとNFTは、単なる技術トレンドではなく、デジタル社会における「価値のあり方」そのものを変える可能性を秘めています。この記事を読んで、その可能性の一端を感じていただけたのではないでしょうか。
Webマーケターや事業企画担当者として次の一歩を踏み出すために、まずは関連ニュースを追いかけたり、少額でNFTを購入して取引を体験してみたりすることをおすすめします。そして、自社での活用を具体的に検討する際には、必ず法務や技術の専門家を交えて、慎重に計画を進めてください。
この記事が、あなたのビジネスに新たな視点をもたらす一助となれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。
- Web3技術の活用方法がわからない
- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい
- NFTを活用したマーケティング施策を検討している
- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい
個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

