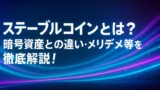ステーブルコインという言葉を耳にするけれど、日本での現状や具体的な活用方法がよくわからない、と感じていませんか?
価格変動の大きな暗号資産と異なり、ステーブルコインは日本円や米ドルなどの法定通貨と価値が連動するため、資産保全や決済手段として注目されています。
ただし、その仕組みや規制、どこで購入できるのかなど、疑問は尽きません。
今回Pacific Meta Magazineでは、日本におけるステーブルコインの現状や取り組み事例について以下の内容について紹介してます。
- ステーブルコインの基本的な仕組み、メリット・デメリット
- 日本におけるステーブルコインの法律や規制の最新動向(2024年改正資金決済法対応)
- 日本国内でのステーブルコイン発行の可能性と実例
- ステーブルコインを購入できる国内取引所の比較と利用方法
- 企業によるステーブルコイン活用事例(決済、地域通貨など)
- 主要な日本円ステーブルコイン(JPYC、Progmat Coinなど)の詳細
日本におけるステーブルコインの全体像を理解し、安全性や将来性を見極めるための一助となるでしょう。
ぜひ、最後までご覧ください。
ステーブルコインとは?― 基本仕組みとメリット・リスクを徹底解説
価格の安定性を目指して設計された特別な種類の暗号資産です。
その価値は、日本円や米ドルといった法定通貨、あるいは金のようなコモディティ(商品)など、特定の資産にペッグ(固定)されることを特徴としています。
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)のような従来の暗号資産が大きな価格変動リスクを抱えているのに対し、ステーブルコインはこの価格変動を最小限に抑えることで、決済手段や価値の保存手段としての実用性を高めています。
日本銀行もステーブルコインを「価値を安定させる仕組みを有し、暗号資産の決済手段としての欠点を解決するもの」と位置づけており、その潜在的な有用性に注目しています。
金融庁の資料においても、ステーブルコインに関する規制の方向性が示されています。
ブロックチェーンとペッグメカニズムの仕組み
ステーブルコインが価格を安定させるためのペッグメカニズムには、主に3つの種類があります。
1. 法定通貨担保型(Fiat-Collateralized Stablecoins)
最も一般的なタイプで、発行されるステーブルコインの価値を、同額の法定通貨(米ドル、日本円など)で裏付けます。
発行体は、発行したステーブルコインの総額と同等かそれ以上の法定通貨を銀行口座などの信頼できる機関に準備金として保管します。
利用者は、この準備金を根拠にステーブルコインの価値を信頼し、いつでも法定通貨と交換(償還)できることが期待されます。
代表例として、USDT(テザー)やUSDC(USDコイン)があります。
2. 暗号資産担保型(Crypto-Collateralized Stablecoins)
他の暗号資産(例:イーサリアム)を担保として発行されるステーブルコインです。
担保となる暗号資産の価格変動リスクを考慮し、通常は発行するステーブルコインの価値以上の暗号資産を担保(過剰担保)として預託する必要があります。
スマートコントラクトによって自動的に担保価値が管理され、一定の担保比率を下回ると清算される仕組みを持つものもあります。
代表例として、DAI(ダイ)があります。
3. 無担保型(アルゴリズム型)(Non-Collateralized / Algorithmic Stablecoins)
特定の担保資産を持たず、アルゴリズムによってコインの供給量を調整することで価格を安定させようとするステーブルコインです。
需要が増えれば供給を増やし、需要が減れば供給を減らすことで、目標価格(例:1ドル)を維持しようとします。
過去にはTerraUSD(UST)のような例がありましたが、その持続可能性や安定性には大きな課題があり、市場の信頼を得るのが難しいタイプとされています。
メリット(価格安定・決済効率)とリスク(規制・流動性)
ステーブルコインの利用には、多くのメリットがある一方で、無視できないリスクも存在します。
- 価格安定性:最大のメリットは、法定通貨などに価値がペッグされていることによる価格の安定性です。これにより、暗号資産取引の際の一次的な資金避難先や、日常的な決済手段としての利用が期待できます。
- 決済効率の向上:ブロックチェーン技術を基盤とするため、従来の銀行送金システムに比べて、特に国際送金などで手数料が安く、迅速な決済が可能です。24時間365日稼働するため、時間や曜日に制約されません。
- 透明性とプログラム可能性:取引記録がブロックチェーン上に記録されるため透明性が高く、スマートコントラクトと組み合わせることで、自動化された決済や複雑な金融取引を実現できる可能性があります。
- 金融包摂:銀行口座を持たない人々でも、スマートフォンとインターネット環境があれば金融サービスへのアクセスが可能になるため、金融包摂の促進に貢献すると期待されています。
- ペッグ維持の不確実性:「ステーブル」とは言っても、完全に価格が固定されているわけではなく、市場の状況や発行体の信用不安などにより、ペッグが外れる(デペッグする)リスクがあります。特にアルゴリズム型ステーブルコインでは、2022年のTerraUSD(UST)の崩壊事例のように、短期間で価値が暴落するケースも発生しました。USDTも過去に一時的なデペッグを経験しています。
- 発行体の信用リスク:法定通貨担保型の場合、発行体が十分な準備金を実際に保有しているか、その管理体制が適切かといった点が重要になります。発行体の破綻や不正行為は、ステーブルコインの価値に直接影響します。
- 規制リスク:各国・地域でステーブルコインに関する法規制の整備が進められていますが、依然として不確実性が高く、新たな規制の導入や変更によって事業モデルが影響を受ける可能性があります。日本では改正資金決済法により規制が明確化されましたが、海外発行のステーブルコインの取り扱いなどには注意が必要です。
- 流動性リスク:特定のステーブルコインの取引量が少ない場合、希望する価格やタイミングで売買できない可能性があります。
- セキュリティリスク:ブロックチェーン技術やスマートコントラクトの脆弱性を突いたハッキングや、ウォレット管理の不備による資産流出のリスクも存在します。
日本の法規制に対応しながら実績を積み重ねている事例と言えます。
これに対し、TerraUSD(UST)の事例は、設計の脆弱性がいかに大きな影響を及ぼすかを示す教訓となっています。
また、下記の記事ではステーブルコインの基礎に焦点を当てた解説を行っています。
ぜひ、こちらもあわせてご覧ください。
日本におけるステーブルコインに関する法律や規制【2024改正対応】
日本におけるステーブルコインの法規制は、2023年6月1日に施行された改正資金決済法によって大きく進展しました。
この改正により、ステーブルコインは「電子決済手段」として法的に位置づけられ、発行者や仲介業者に対するルールが明確化されました。
これにより、利用者保護の強化とマネーロンダリング及びテロ資金供与(AML/CFT)対策の徹底が図られています。
金融庁は、関連する政令や内閣府令、ガイドラインを公表しており(詳細は金融庁ウェブサイト https://www.fsa.go.jp/ を参照)、国際的な議論の場であるFATF(金融活動作業部会、https://www.fatf-gafi.org/)の勧告も踏まえた対応が進められています。
資金決済法・利用者保護の概要
改正資金決済法におけるステーブルコイン(電子決済手段)の規律の核心は、利用者保護の強化です。
まず、電子決済手段は「法定通貨建て(円建て、ドル建て等)」であり、「発行価格と同額で償還されるもの」と定義され、発行者に対して厳格な財産保全義務が課せられました。
具体的には、発行者は利用者の資金を信託銀行への信託、銀行預金、あるいは保証金の供託といった形で保全しなければなりません。
これにより、万が一発行者が破綻した場合でも、利用者の資金は優先的に弁済される仕組みとなっています。
発行主体となれるのは、銀行、資金移動業者、信託会社、そして新たに設けられた「電子決済手段等取引業者」のライセンスを取得した者に限定されます。
これらの発行者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、財務基盤や業務運営体制に関する厳しい審査をクリアしなければなりません。
また、電子決済手段の仲介業務(売買、交換、媒介、取次、代理など)を行う事業者も「電子決済手段等取引業者」としての登録が必要となり、本人確認義務(KYC)、疑わしい取引の届出義務(STR)などのAML/CFT要件を遵守することが求められます。
これらの規制は、ステーブルコインの信頼性を高め、利用者が安心して取引できる環境を整備することを目的としています。
違反した場合には、業務停止命令や登録取消、罰金などの厳しい罰則が科される可能性があります。
2023‑24年改正ポイントと最新ガイドライン
2023年6月1日に施行された改正資金決済法および関連政省令・ガイドラインは、日本におけるステーブルコインの取り扱いを大きく変えました。
最大のポイントは、ステーブルコインを「電子決済手段」として法的に定義し、その発行・仲介に関するルールを明確化した点です。
これにより、それまで法的位置づけが曖昧だったステーブルコインについて、発行者ライセンス制度が導入され、利用者保護のための財産保全義務やAML/CFT対策が義務付けられました。
金融庁が公表した「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16.電子決済手段等関連業務を行う電子決済手段等取引業者関係)」(金融庁ウェブサイトで確認可能)では、具体的な要件や解釈が示されています。
日本で発行される主なステーブルコインの類型としては、以下のようなものが想定されています。
- 銀行等による発行(預金トークン型):銀行が発行するものは、預金保険の対象となる預金を裏付けとする「預金トークン」として扱われます。
- 資金移動業者による発行:資金移動業者が発行するものは、為替取引に係る債務として扱われ、履行保証金の供託などによる資産保全が求められます。
- 信託会社による発行(信託型):信託会社が発行するものは、信託受益権をトークン化した形式をとり、信託財産として分別管理されるため、発行者の破綻リスクから隔離されます。JPYCがこのスキームでの発行を目指しています。
- 特定信託受益権等に係る電子決済手段(金商法上の扱い):一部のステーブルコインは、その性質上、金融商品取引法の規制対象となる可能性も考慮されています。
2024年に入ってからも、これらの法制度の運用状況や国際的な動向を踏まえ、金融庁は必要に応じてガイドラインの見直しやQ&Aの公表を行っており、市場関係者は常に最新情報を確認する必要があります。
以下に、簡略化した分類表のイメージを示します。(実際の図表は金融庁資料等をご参照ください)
| 分類 | 発行主体(例) | 法的根拠(主たるもの) | 資産保全方法(例) |
|---|---|---|---|
| 預金トークン型 | 銀行 | 預金保険法、銀行法 | 預金保険 |
| 資金移動型 | 資金移動業者 | 資金決済法 | 履行保証金供託 |
| 信託型 | 信託会社 | 信託法、資金決済法 | 信託財産として分別管理 |
| (旧)前払式支払手段型 | (発行終了・移行予定) | (資金決済法) | (発行保証金供託) |
日本でステーブルコインは発行できる?― 信託スキームと実例
2023年6月の改正資金決済法施行により、日本国内でステーブルコインを「電子決済手段」として発行するための法的な道筋が整備されました。
これにより、一定の要件を満たした事業者は、内閣総理大臣の登録を受けることで、日本円や米ドルなどにペッグされたステーブルコインを発行・流通させることが可能になります。
発行主体としては、銀行、資金移動業者、信託会社などが想定されており、それぞれ異なるスキームとライセンス要件が適用されます。
発行コストは、選択するスキーム、システム構築、法務・コンプライアンス体制の整備、そして継続的な監査やセキュリティ対策など、多岐にわたる要素によって大きく変動します。
発行スキームと信託/担保モデル
日本でステーブルコインを発行する際の主なスキームと、それに伴う信託・担保モデルは以下の通りです。
1. 銀行による発行(預金トークン型)
銀行が発行主体となる場合、そのステーブルコインは銀行の預金債務をトークン化したものとして扱われます。
この場合、預金保険制度の対象となり得るため、利用者保護の観点からは高い信頼性が期待できます。
銀行は既存の銀行法ライセンスに基づき発行可能ですが、システム対応やリスク管理体制の構築が必要です。
2. 資金移動業者による発行
資金移動業者が発行主体となる場合、ステーブルコインは為替取引(送金)の手段として発行されます。
発行者は、発行額に応じた履行保証金を法務局に供託するか、信託銀行等との保全契約を結ぶことで資産保全を行う義務があります。
第二種資金移動業(100万円超の送金)または第一種資金移動業(100万円以下の送金)のライセンスが必要となります。
3. 信託会社による発行(信託型)
信託会社が発行主体となる場合、利用者が払い込んだ法定通貨を信託財産として受け入れ、その信託受益権をトークン化した形でステーブルコインを発行します。
このモデルの大きな特徴は、信託財産が信託会社の固有財産とは分別管理されるため、発行体である信託会社が破綻しても、利用者の資産は保全されるという点です(倒産隔離)。
JPYCがこの信託型スキームでの発行を目指して三菱UFJ信託銀行などと提携しています。
これらの発行モデルにおいて、担保となる資産(裏付け資産)は、原則として発行額と同額以上の法定通貨(銀行預金など安全性の高い資産)で保全されることが求められます。
これにより、ステーブルコインの価値の安定性と償還の確実性が担保されます。
国内発行事例:JPYC・Progmat Coinほか
改正資金決済法の施行を受け、日本国内でもステーブルコイン発行に向けた動きが活発化しています。
JPYC(ジェイピーワイシー)
JPYC株式会社が発行する日本円連動型ステーブルコイン「JPYC」は、改正法施行前から前払式支払手段として発行・流通していました。
2023年11月には、三菱UFJ信託銀行およびProgmat社との提携を発表し、改正法に対応した信託型ステーブルコインとして再発行する計画を進めています。
これにより、JPYCは電子決済手段としてのライセンス取得を目指し、より広範なユースケースに対応できるようになることが期待されています。
JPYCの公式サイトでは、最新情報が公開されています。
Progmat Coin(プログマコイン)
三菱UFJ信託銀行が開発を主導するステーブルコイン発行管理基盤「Progmat Coin」は、様々な企業が独自のブランドでステーブルコインを発行できるプラットフォームです。
この基盤上で発行されるステーブルコインは、信託スキームを活用し、改正資金決済法に準拠した形で提供される予定です。
三菱UFJ信託銀行自身が発行する円建てステーブルコインのほか、他の銀行や事業会社が発行体となり、それぞれのニーズに応じたステーブルコイン(例:米ドル建て、ユーロ建て)を発行することが構想されています。
みずほフィナンシャルグループもProgmatを活用した企業間決済向けステーブルコインの発行を検討しており、2024年以降の実用化を目指しています。
その他の動向
上記以外にも、複数の金融機関やIT企業がステーブルコインの発行や関連サービスの開発を検討していると報じられています。
SBIグループも過去に「Sコイン」構想を発表するなど、ステーブルコイン分野への関心を示しています。
今後、具体的な発行事例が増えてくることが予想されます。
将来の発行モデルと課題
将来的には、日本国内で多様な発行モデルが登場し、ステーブルコインの利用シーンが拡大することが期待されます。
例えば、特定の経済圏(例:ゲームプラットフォーム、地域コミュニティ)で利用される独自のステーブルコインや、特定の目的(例:サプライチェーンファイナンス、不動産取引決済)に特化したステーブルコインなどが考えられます。
また、クロスチェーン技術の発展により、異なるブロックチェーン上で発行されたステーブルコイン間の相互運用性が向上し、利便性が高まる可能性もあります。
しかし、これらの将来モデルを実現するためには、いくつかの課題も存在します。
1. 規制の明確性と柔軟性のバランス
イノベーションを促進しつつ、利用者保護や金融システムの安定性を確保するためには、規制当局による明確かつ実態に即したガイダンスの継続的な提供が不可欠です。
過度な規制は市場の成長を妨げる可能性がある一方、規制が緩すぎればリスクが増大します。
2. 技術的課題とセキュリティ
ステーブルコインを発行・運用するためのブロックチェーン基盤の処理能力(スケーラビリティ)、セキュリティ、そして相互運用性の確保は依然として重要な課題です。
特に、ハッキングやシステム障害に対する堅牢な対策が求められます。
3. ビジネスモデルの確立と収益性
ステーブルコインの発行・運営にはコストがかかります。
発行体が持続的に事業を継続できるような、適切なビジネスモデルと収益源を確立する必要があります。
特に、金利収入が見込めない日本円建てステーブルコインの場合、手数料収入や付加価値サービスによる収益化が鍵となります。
4. 利用者への啓発とリテラシー向上
ステーブルコインの仕組みやリスクについて、利用者の理解を深めるための啓発活動も重要です。
特に、秘密鍵の管理や詐欺被害の防止など、セキュリティ意識の向上が求められます。
これらの課題を克服し、信頼性の高いステーブルコインが普及することで、日本のデジタル金融は新たなステージに進むことができるでしょう。
ステーブルコインを扱う日本の取引所はある?
日本国内でステーブルコインを購入・利用する方法は、2023年の改正資金決済法施行以降、徐々に整備されつつあります。
これまでは海外の暗号資産取引所を利用するか、JPYCのように発行元から直接購入する方法が主でしたが、今後は国内の暗号資産交換業者(取引所)でも取り扱いが始まる見込みです。
ここでは、国内取引所におけるステーブルコインの取り扱い状況や、手数料、購入手順などについて解説します。
国内取引所の取り扱い状況一覧
2025年5月現在、日本国内の暗号資産交換業者におけるステーブルコインの取り扱いは限定的ですが、大手取引所を中心に準備が進められています。
特に米ドル連動型ステーブルコインであるUSDコイン(USDC)の取り扱い開始が複数の取引所で予定されています。
| 取引所名 | 取扱予定ステーブルコイン | 対応ネットワーク(予定) | 備考 |
|---|---|---|---|
| SBI VCトレード | USDC | 未定(詳細発表待ち) | 2025年前半の取扱開始を目指す |
| コインチェック | USDC | 未定(詳細発表待ち) | 2025年の早い段階での取扱開始を目指す |
| bitFlyer | (検討中・公表情報なし) | – | – |
| GMOコイン | (検討中・公表情報なし) | – | – |
| JPYC株式会社(発行元) | JPYC(信託型) | Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Astar, Shiden, Gnosisなど(既存の前払式JPYC。信託型もマルチチェーン対応予定) | 取引所ではなく発行元から購入。信託型への移行準備中。 |
日本円建てステーブルコインについては、JPYC(信託型)が発行され次第、公式サイトなどを通じて購入可能になる見込みです。
また、Progmat Coin基盤上で発行される各種ステーブルコインも、それぞれの発行体の計画に応じて提供方法が決定されると考えられます。
海外で広く利用されているテザー(USDT)については、現時点では国内取引所での取り扱い予定は公表されていません。
これは、USDTの発行体であるテザー社が日本の電子決済手段等取引業者のライセンスを取得していないことや、準備金の透明性に関する議論などが背景にあると考えられます。
手数料・スプレッド・送金速度を実測
国内取引所でステーブルコインを取引する際にかかる手数料や、送金速度は、利用者にとって重要な選択基準となります。
(このセクションは、国内取引所でステーブルコインの取り扱いが本格的に開始された後、実際のデータに基づいて詳細な比較情報を提供する予定です。以下は一般的な注意点です。)
手数料の種類
- 取引手数料
- 入出金手数料
- スプレッド
送金速度
ステーブルコインの送金速度は、主に利用するブロックチェーンネットワークの種類に依存します。
一般的に、ブロックチェーン上でのステーブルコイン送金はほぼ即時から数分以内で完了することが多いです。
世界銀行の調査によれば、従来の国際送金コストが平均6.35%であるのに対し、ステーブルコイン利用時のコストは平均0.5~3.0%程度と報告されています。
実測について
「実際の送金コスト比較」や「手数料・スプレッド・送金速度を実測」に関する詳細なレポートは、サービス提供開始後に改めて検証し、情報を提供する予定です。
実践ガイド:購入からウォレット送金まで
国内取引所でステーブルコインを購入し、個人のウォレット(例:MetaMask)に送金するまでの一般的な手順は以下の通りです。
ステップ1:国内取引所の口座開設と本人確認
- 取引所を選び、口座開設を申し込みます。
- 本人確認書類を提出し、審査を待ちます。
- 審査が完了すると、口座が開設されます。
ステップ2:日本円の入金
- 口座に日本円を入金します。
- 入金方法は銀行振込やクイック入金などが一般的です。
ステップ3:ステーブルコインの購入
- 取引所の取引画面で購入したいステーブルコインを選択します。
- 購入数量または日本円金額を指定し、注文します。
- 約定すると、ステーブルコインが口座に反映されます。
ステップ4:個人のウォレットへの送金(出金)
- 出金メニューでステーブルコインと送金先アドレスを指定します。
- 二段階認証などを経て、送金を実行します。
- ブロックチェーン上で処理され、ウォレットに反映されます。
Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから
⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード
日本でのステーブルコインの企業の取組動向
日本国内の企業においても、ステーブルコインの持つ価格安定性や決済効率の高さに着目し、その活用に向けた取り組みが進んでいます。
特に、企業間決済の効率化、新たな決済サービスの創出、そして地域経済の活性化を目指した地域通貨としての活用などが検討・実証されています。
改正資金決済法の施行により法的環境が整備されたことで、これらの動きは今後さらに加速すると予想されます。
三菱UFJ信託銀行のProgmat Coinに関する取り組みや、農林水産省がまとめた地域通貨に関する実証事例などが参考になります。
企業決済・送金事例(みずほ・楽天等)
企業間(B2B)決済や国際送金におけるステーブルコインの活用は、コスト削減と迅速化の観点から大きな期待が寄せられています。
メガバンクの取り組み
三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)とみずほフィナンシャルグループは、企業間決済向けのステーブルコイン発行に関して協調する動きを見せています。
三菱UFJ信託銀行が開発する「Progmat Coin」を共同で活用し、2024年以降に企業間決済に特化したステーブルコインを実用化する計画が報じられています。
楽天グループの動向
楽天グループは、ブロックチェーン技術や暗号資産に関心を示しており、将来的には楽天エコシステム内での決済手段としてステーブルコインを活用する可能性があります。
ただし、具体的な発行計画は公表されていません。
その他企業の検討
多くの企業がサプライチェーンにおける決済効率化、クロスボーダー取引の円滑化、社内資金管理の最適化などを目的として、ステーブルコインの導入を検討しています。
海外との取引が多い商社やメーカーなどでは、手数料や決済期間の短縮が大きなメリットとなります。
地域通貨・自治体実証実験
ステーブルコインの技術は、地域経済の活性化や特定のコミュニティ内での利用を目的としたデジタル地域通貨にも活用されています。
これらは、日本円にペッグされたステーブルコインとして発行され、スマートフォンアプリなどを通じて利用されるケースが多いです。
主な目的とメリット:
- 地域内消費の促進
- キャッシュレス化の推進
- 事務コストの削減
- データ活用
国内の実証実験事例:
「さるぼぼコイン」「アクアコイン」などの地域通貨が運用されています。
健康増進活動に応じて地域通貨が付与されるモデルや、ブロックチェーン技術を活用した地域通貨の倫理的消費への応用など、多彩な実証実験が進められています。
大企業・金融機関のPoCと投資動向
大手企業や金融機関は、ステーブルコインの実用化に向けて、様々なPoCや戦略的投資を行っています。
既存の金融インフラを補完・代替し得る技術として、ステーブルコインを活用する動きが加速しています。
PoCの主な領域としては、企業間決済、セキュリティトークン決済、サプライチェーンファイナンス、クロスボーダー送金などが挙げられます。
投資動向としては、NTTデータやVisa、Mastercardなどがステーブルコイン関連技術を持つ企業への出資や提携を積極的に行っています。
PayPalも独自の米ドル建てステーブルコイン「PYUSD」を発行開始しました。
下記の記事では、国内企業のブロックチェーンの活用事例を紹介しています。
ぜひ、こちらもあわせてご覧ください。
日本円ステーブルコイン主要銘柄比較ガイド(JPYC/Progmat Coin/SBI)
日本国内で注目される日本円連動型ステーブルコインとしては、既に流通しているJPYCや、発行が計画されているProgmat Coin基盤のステーブルコイン、そしてSBIグループが構想するステーブルコインなどがあります。
これらのステーブルコインは、それぞれ発行スキームや特徴、想定されるユースケースが異なります。
JPYC ― プリペイド型ステーブルコインの先駆者
JPYCは、JPYC株式会社によって発行されている日本初の日本円連動型ステーブルコインです。
1 JPYC = 1円で取引され、複数のブロックチェーン上で利用可能です(マルチチェーン対応)。
- 仕組みと特徴:改正法施行前は「自家型前払式支払手段」として発行されていましたが、現在は信託型への移行が計画されています。利用者が払い込んだ日本円は信託銀行に信託され、信託受益権をトークン化した形でJPYCが発行されることで、倒産隔離が期待できます。
- 手数料:購入・売却(償還)手数料やネットワーク手数料(ガス代)がかかる場合があります。新たな信託型JPYCでの手数料体系は正式リリース後に明らかになる見込みです。
- 流通量:累計発行額は2023年11月時点で約23億円。信託型への移行でさらなる成長が期待されています。
Progmat Coin ― 信託型インフラの次世代モデル
Progmat Coinは、三菱UFJ信託銀行が開発するステーブルコインの発行・管理プラットフォームです。
信託受益権を裏付けに、複数の金融機関や事業会社が独自のコインを発行できる設計になっています。
- 仕組みと特徴:信託会社の倒産隔離機能を活かし、ユーザー資産を安全に保全できる点が最大の特長です。企業間決済やセキュリティトークン決済での利用を見据えて開発されています。
- 手数料:発行体によって異なる見込み。プラットフォーム利用料や送金手数料などが想定されます。
- 流通量(計画):大手銀行・企業が参画予定のため、市場導入後の流通規模は大きくなる可能性があります。
SBI系「Sコイン」プロジェクトの全貌
SBIグループは「Sコイン」という名称で独自のステーブルコイン構想を持っています。
銀行、証券、暗号資産交換業など幅広い金融事業を展開するグループ力を活かし、さまざまなユースケースを想定しているとみられます。
- 仕組みと特徴(構想段階):日本円ペッグ型ステーブルコインになる見込み。具体的な発行スキームは未公表ですが、改正資金決済法の要件を満たす形が想定されます。
- 手数料:サービス開始時に公表される見込みです。
- 流通量(計画):SBIグループの顧客基盤を活かし、大規模な流通を目指す可能性があります。
| 項目 | JPYC(信託型予定) | Progmat Coin基盤のSC(例) | SBI系「Sコイン」(構想) |
|---|---|---|---|
| 発行主体(主導) | JPYC株式会社 (信託:三菱UFJ信託など) | 三菱UFJ信託銀行、 他金融機関・企業 | SBIグループ |
| ペッグ通貨 | 日本円 | 日本円や米ドルなど | 日本円(想定) |
| 発行スキーム | 信託型電子決済手段 | 信託型電子決済手段 | 未定 |
| ブロックチェーン基盤 | マルチチェーン(Ethereum等) | 複数チェーン対応予定 | 未定 |
| 主なユースケース | 個人・法人決済、DeFi | 企業間決済、ST決済 | グループ内決済など |
| 資産保全 | 信託財産による倒産隔離 | 信託財産による倒産隔離 | 法令準拠の保全措置 |
| 購入方法(予定) | 公式サイト、 提携販売所など | 発行体が決定 | 未定 |
| 流通状況 | 前払式は既に流通中。 信託型は準備中 | PoC実施中。 2024年以降に本格化 | 構想段階 |
日本におけるステーブルコインの現状についてよくある質問
ここでは、ステーブルコインについてよくある質問とその答えを紹介します。
日本でステーブルコインは合法ですか?
日本でステーブルコインを利用することは合法です。
ただし、厳格な規制下に置かれています。
2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、ステーブルコインは「電子決済手段」として位置づけられました。
発行者や仲介業者はライセンス取得が必要で、利用者保護やAML/CFT要件を遵守しなければなりません。
海外発行のステーブルコインも保有自体は可能ですが、国内業者が取り扱う場合は日本の規制要件を満たす必要があります。
どの国内取引所で購入できますか?
2025年5月現在では取り扱いが限定的ですが、SBI VCトレードやコインチェックなどが米ドル連動型ステーブルコイン(USDC)の取り扱いを準備しています。
日本円建てステーブルコインのJPYCは、これまで発行元(JPYC社)から直接購入可能でした。
今後は信託型JPYCの発行に伴い、取り扱いチャネルが拡大される見込みです。
各取引所の公式サイトや当サイトの「取引所比較」ページなどで最新情報をご確認ください。
CBDC(デジタル円)との違いは?
CBDCは中央銀行が発行する法定通貨そのものであり、ステーブルコインは民間企業による私的なデジタル通貨という違いがあります。
CBDCは国家の信用を裏付けとしており信用リスクが極めて低い一方、ステーブルコインは発行体の信用や準備資産に依存します。
日本銀行のウェブサイトでもCBDCに関する情報が公開されています。
税金・確定申告の扱いは?
ステーブルコインの売却益や他の暗号資産との交換益は、原則として雑所得として課税対象となり、確定申告が必要です。
日本円建てステーブルコインの場合は価値変動が小さいため利益が発生しにくい面もありますが、手数料なども考慮する必要があります。
法人の場合は会計上の取り扱いが異なる可能性がありますので、税理士など専門家にご相談ください。
海外ステーブルコインを日本で使うリスクは?
海外発行のステーブルコイン(USDTなど)を日本国内で個人が利用すること自体は可能ですが、発行体の信用リスクや規制リスク、トラブル時の対応が困難といった問題があります。
日本の利用者保護や財産保全制度の対象外となる場合も多いため、注意が必要です。
無登録の海外業者との取引は金融庁も注意喚起を行っています。
日本におけるステーブルコインの現状についてまとめ
今回、Pacific Meta Magazineでは、ステーブルコイン日本について以下の内容を紹介してきました。
- ステーブルコインは法定通貨などに価値が連動する暗号資産で、価格安定性や決済効率向上がメリットだが、発行体の信用リスクや規制リスクも存在する。
- 日本では2023年改正資金決済法により「電子決済手段」と定義され、発行・仲介にはライセンスが必要となり、利用者保護が強化された。
- JPYCやProgmat Coin基盤のステーブルコインなど、国内でも発行事例や計画が登場し、企業間決済や地域通貨での活用が期待されている。
- 国内取引所でもUSDCなどの取り扱いが開始予定であり、購入・利用の選択肢が増えつつあるが、手数料や対応ネットワークの確認が重要。
- 税務上は他の暗号資産と同様に雑所得として扱われる可能性が高く、CBDCとは発行主体や信用の裏付けが異なる。
日本におけるステーブルコイン市場は、法整備という大きな一歩を経て、まさにこれから本格的な普及期を迎えようとしています。
その仕組みやメリットを理解し、リスクを適切に管理することで、個人投資家にとっては新たな資産保全や送金の選択肢となり、企業にとっては決済効率化や新規事業創出のツールとなり得ます。
特に日本円建てステーブルコインの登場は、国内でのユースケースを大きく広げる可能性を秘めています。
今後の技術動向や各社のサービス展開、そしてさらなる規制の明確化に注目しつつ、ご自身の目的に合わせてステーブルコインの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。
- Web3技術の活用方法がわからない
- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい
- NFTを活用したマーケティング施策を検討している
- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい
個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。