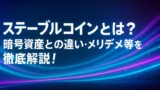Web3を活用した新規事業を検討する中で、「日本円ステーブルコイン」というキーワードを目にする機会が増えたものの、その複雑な仕組みや法規制に頭を悩ませていませんか?
ドル建てステーブルコインの情報は多い一方、日本円に特化した実務的な情報は少なく、自社サービスへの導入判断に踏み切れない担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回、Pacific Meta Magazineでは、日本円ステーブルコインについて以下の内容について紹介してます。
- 日本円ステーブルコインの定義と円連動を支える仕組み
- 企業が導入する具体的なメリットとコスト削減効果
- 2025年最新の資金決済法を中心とした法規制のポイント
- 国内主要銘柄「JPYC」の仕組み、リスク、他コインとの比較
- 導入に向けた購入方法から会計・税務処理までの実務フロー
本記事では、金融庁の資料などの一次情報や実務事例を基に、事業担当者が知るべき情報を網羅的に解説します。ぜひ、最後までご覧ください。
日本円ステーブルコインとは?定義・円連動メカニズムと市場動向

日本円ステーブルコインは、デジタル資産の利便性と法定通貨の安定性を兼ね備えた、Web3時代の新たな決済インフラとして注目されています。その本質を理解するためには、まず基本的な定義、価格を安定させる仕組み、そして最新の市場動向を正確に把握することが不可欠です。
日本円ステーブルコインの定義と基礎
ステーブルコインとは、ブロックチェーン上で発行される暗号資産の一種であり、価格が特定の資産と連動するように設計されたトークンです。その中でも、価値が「日本円」に連動するように作られたものが日本円ステーブルコインと呼ばれます。常に「1コイン≒1円」の価値を維持することを目指しており、価格変動が激しいビットコインなどとは一線を画します。
2023年6月に施行された改正資金決済法では、この種のステーブルコインは「電子決済手段」として法的に位置づけられました。これは、日本円などの法定通貨で償還が約束されているなど、一定の要件を満たすものを対象としています。この法整備により、従来の「暗号資産」とは異なる、金融庁の監督下にある決済手段として明確に定義され、企業が事業に活用する上での信頼性が大きく向上しました。
円連動を実現する価格安定メカニズム
ステーブルコインが安定した価値を保つための仕組み(メカニズム)は、大きく3つに分類されます。日本の法規制下では、特に資産を裏付けとする方式が重要視されています。
- 資産担保型(準備金方式):発行したステーブルコインの総額と同等以上の価値を持つ法定通貨や短期国債などの資産を「準備金」として発行者が保有する方式です。利用者はいつでもステーブルコインを準備資産に交換できるため、信頼性が担保されます。世界的に流通するUSDCやUSDTはこのモデルを採用しています。
- 信託保全型(信託方式):資産担保型の一種で、日本の「電子決済手段」で中心的な役割を担う方式です。準備資産を発行者の財産から法的に切り離し、信託銀行などの信託会社に預けます。この仕組みにより、仮に発行事業者が倒産しても、利用者の資産は信託法によって保全される(倒産隔離)ため、極めて高い利用者保護が実現されます。三菱UFJ信託銀行などが推進する「Progmat Coin」がこのモデルの代表例です。
- アルゴリズム方式:特定の資産を裏付けとせず、スマートコントラクトによってトークンの供給量を自動調整し、価格を安定させようとする方式です。過去にTerra/LUNAの価格が暴落した事例もあり、市場の急変動に弱いというリスクを抱えています。日本の現行法では「電子決済手段」として認められていません。
事業で活用する際は、この価格安定の仕組みを理解し、特に資産保全性の高い信託保全型や準備金方式のステーブルコインを選択することがリスク管理の観点から重要です。
国内外市場規模とトレンド(2025年最新版)
世界のステーブルコイン市場は急速に拡大しており、2025年初頭には時価総額が2,000億ドル(約30兆円)を突破しました。市場シェアは依然として米ドルに連動するUSDTとUSDCが大部分を占め、グローバルなデジタル資産取引の基軸通貨としての地位を確立しています。
この成長を背景に、米シティグループは2030年までに市場が最大3兆7,000億ドル規模に達するとの強気な予測を発表しています。2025年は、日本や米国をはじめとする主要国で規制の枠組みが明確化されたことで、ステーブルコイン普及の「転換点」になると見なされています。これにより、これまで参入をためらっていた大手金融機関や事業会社の本格的な参入が加速すると考えられます。
日本国内では、改正資金決済法を追い風に、複数の大手金融機関やFinTech企業が日本円ステーブルコインの発行準備を進めており、今後、発行残高は急速に増加していくことが予想されます。
下記の記事ではステーブルコインの基礎に焦点を当てた解説を行っています。
そもそもステーブルコインとは?という疑問をお持ちの方は、こちらもあわせてご覧ください。
日本円のステーブルコインが発行されるメリットとは?

日本円ステーブルコインの導入は、単に決済手段が増えるだけでなく、企業のコスト構造や業務効率、さらには新たなビジネスチャンスの創出に直結する戦略的なメリットをもたらします。
企業・ユーザーのメリット一覧
企業やユーザーが享受できる主なメリットは以下の通りです。
- 劇的なコスト削減:従来の銀行送金やクレジットカード決済で発生していた数%の手数料を大幅に削減できます。ブロックチェーン上で直接価値を移転するため、仲介者が減り、取引コストを低く抑えることが可能です。加盟店手数料を0.5%程度に設定できる可能性も示唆されており、企業の収益改善に直結します。
- 24時間365日の即時決済:銀行の営業時間に縛られず、いつでもリアルタイムでの送金・決済が完了します。これにより、売掛金の回収サイクル短縮によるキャッシュフローの改善や、週末・夜間取引といった新たなビジネスモデルの実現が期待できます。
- プログラマビリティによる業務革新とUX向上:スマートコントラクトを活用し、「商品が納品されたら代金を自動で支払う」といった商流と金流を連動させた自動決済や、複雑なロイヤリティ分配の自動化が可能です。手作業をなくすことで業務効率が向上し、ヒューマンエラーも削減できます。
国内キャッシュレス決済とのシナジー
PayPayなどのQRコード決済は特定のプラットフォームに閉じた「クローズド」なシステムですが、ステーブルコインは特定の事業者に依存しない「オープン」なプロトコル上で機能します。このオープン性が、既存のキャッシュレス決済にはない新たな価値を生み出します。
例えば、あるゲームアプリで獲得したステーブルコインを、別のECサイトでの支払いに直接利用したり、企業の基幹システムと連携させてサプライチェーン上の取引を自動決済したりするなど、プラットフォームの垣根を越えた連携が可能です。これは消費者向け決済(B2C)の効率化に留まらず、企業間取引(B2B)やM2M(Machine-to-Machine)コマースといった次世代の経済活動の基盤となる可能性を秘めています。
国際送金・DeFi活用での競争優位
日本企業がWeb3事業を行う際、USDCなどの米ドル建てステーブルコインを利用すると、必然的に為替変動リスクにさらされます。日本円をドル建てコインに交換した時点で為替ポジションを持つことになり、その後の円相場の変動が企業の財務に直接影響を与えてしまいます。
日本円ステーブルコインは、この問題を根本的に解決します。企業は自国通貨である円を基準としたデジタル資産を利用することで、為替リスクを完全に排除し、財務・経理プロセスを大幅に簡素化できます。これは単なるコスト削減ではなく、事業の予見可能性を高め、経営リスクを低減するという、非常に大きな戦略的優位性です。これにより、日本の投資家や企業は、海外のDeFi(分散型金融)サービスを利用する際にも、為替を気にすることなく円建てで参加できるようになります。
日本円ステーブルコインの法規制と資金決済法との関係とは?
日本円ステーブルコインを事業で安全に活用するためには、その法的枠組みを正しく理解することが不可欠です。日本では世界に先駆けて包括的な規制が整備されており、その中核をなすのが「資金決済に関する法律(資金決済法)」です。
資金決済法における電子決済手段の位置付け
2023年6月1日に施行された改正資金決済法は、日本円などの法定通貨の価値に連動し、発行価格と同額での償還が約束されたステーブルコインを「電子決済手段」と新たに定義しました。この法律は、エコシステムに関わるプレイヤーを「発行者」と「仲介者」に明確に分け、それぞれに異なるライセンスを要求しています。
- 発行者:電子決済手段の発行と償還を行う主体。銀行、信託会社、資金移動業者のいずれかに限定され、高い信頼性が求められます。
- 仲介者:電子決済手段の売買や交換、管理(カストディ)を行う主体。暗号資産交換業者やウォレット事業者が該当し、「電子決済手段等取引業」としての登録が必要です。
この改正により、JPYCなどがこれまで準拠してきた「前払式支払手段」(プリペイドカードや電子マネーなど、原則払い戻し不可)とは明確に区別され、円貨での償還が法的に保証された、より通貨に近い存在として位置づけられました。
2025年改正ポイントとパブリックコメント要旨
金融規制は常に進化しており、2025年施行予定の改正案ではさらなる見直しが検討されています。金融庁の資料によると、特に注目されるのが、信託型ステーブルコインの裏付け資産の運用方法の柔軟化です。現行法では、裏付け資産は全額を銀行預金で保有する必要がありますが、改正案では発行額の一部を上限に、元本毀損リスクの低い国債などでの運用を認めることが提案されています。
この変更は、発行者にとって新たな収益源を生み出し、ステーブルコイン発行事業の採算性を向上させる可能性があります。結果として、より多くの金融機関の参入を促し、市場の競争が活性化することで、利用者である企業はより低コストで質の高いサービスを享受できると期待されます。
過去のパブリックコメントでは、金融庁がパブリックチェーン上での発行に対して慎重な姿勢を示すなど、イノベーションとリスク管理のバランスを図る姿勢がうかがえます。
発行・管理に必要なライセンス/監督体制
企業が安全に日本円ステーブルコインを利用するためには、取引相手となる事業者が適切なライセンスを持ち、監督下にあるかを確認することが極めて重要です。
- 発行者の確認:取引するステーブルコインの発行者が、銀行・信託会社・資金移動業者のいずれかのライセンスを保有しているか。
- 仲介者の確認:利用する取引所が「電子決済手段等取引業」として金融庁に登録されているか。
- 資産保全の確認:発行済みコインに対し、100%の裏付け資産が信託などの法律で定められた方法で保全されているか。
- AML/KYC体制の確認:マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)が厳格に整備され、トラベルルール(送金者と受取人の情報を交換する規則)に対応しているか。
- 監査要件の確認:システムのセキュリティや資産の管理状況について、第三者機関による定期的な監査を受けているか。
これらの点をチェックリストとして活用し、コンプライアンスを遵守している事業者と取引することが、リスクを管理する上で不可欠です。
日本円ステーブルコインJPYCの仕組みと特徴とは?
JPYCは、日本国内で最も早くから流通している代表的な日本円ステーブルコインです。その仕組みと特徴を理解することは、国内のステーブルコイン市場の動向を把握する上で欠かせません。
JPYCのトークン化スキームと技術スタック
技術的に、JPYCはイーサリアムブロックチェーン上で広く採用されている「ERC-20」という標準規格に準拠したトークンです。これにより、世界中の多くのウォレットや分散型アプリケーション(dApps)との高い互換性を持ち、イーサリアムの広大なエコシステムでシームレスに利用できます。
JPYCの大きな特徴の一つが、マルチチェーン戦略です。イーサリアムだけでなく、取引手数料(ガス代)が安価で処理速度が速いPolygon、Astar、Arbitrumなど、複数のブロックチェーン上でも発行されています。これにより、ユーザーは少額決済や高頻度の取引など、用途に応じて最適なネットワークを選択することが可能です。
法的な側面では、JPYCは大きな転換期にあります。当初は「自家型前払式支払手段」として発行されていましたが、2025年6月でその新規発行を終了し、今後は改正資金決済法に準拠した「電子決済手段」としての発行を目指しています。これを実現するため、発行元のJPYC株式会社は現在、第二種資金移動業のライセンス取得を進めており、取得後は1JPYC=1円での償還が法的に保証されることになります。
信託保全・発行残高の透明性
資産保全に関して、JPYCはこれまで前払式支払手段として、法律に基づき発行残高の50%以上に相当する額を「発行保証金」として法務局に供託してきました。これは発行者の破綻時に利用者を保護するための制度です。今後は資金移動業者として、利用者資金を信託勘定や分別管理された銀行口座で保全するなど、より強固な利用者保護措置を講じることになります。
透明性の確保にも力を入れており、JPYCのスマートコントラクトは第三者の専門機関によるセキュリティ監査を受けています。また、各ブロックチェーン上のコントラクトアドレスは公開されており、ブロックエクスプローラー(Etherscanなど)を使えば、誰でも発行量や取引履歴をリアルタイムで追跡することが可能です。これを「Proof of Reserve(準備金の証明)」と呼び、オンチェーンでの透明性を担保しています。
主要ブロックチェーン別の対応状況
JPYCのマルチチェーン対応は、企業にとって実用的なコストメリットをもたらします。例えば、イーサリアムメインネットは高いセキュリティを誇りますが、ネットワークが混雑するとガス代が数千円に達することもあります。一方、PolygonやAstar、Arbitrumといったレイヤー2や互換チェーンでは、ガス代を数円から数十円程度に抑えることが可能です。
これにより、マイクロペイメント(少額決済)や、ポイントプログラムの報酬配布、ゲーム内アイテムの売買など、これまで手数料の観点から実現が難しかったユースケースへの応用が現実的になります。企業は自社のサービス特性に合わせて、セキュリティとコストのバランスが最適なブロックチェーンを選択してJPYCを導入することができます。
Pacific Metaでは「Web3領域での事業開発に課題を抱えている」「ブロックチェーン技術を事業に取り入れたいがどう活用すべきか分からない」企業様を包括的にサポートします。ブロックチェーンやNFTといったWeb3技術を活用した新規事業の立ち上げから、市場ニーズに適合した事業企画の策定から実行まで、トータルでご支援いたします。Web3を活用した新規事業展開をご検討中の方は、ぜひご連絡ください。
⇒ サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちらから
⇒ CASIO様との海外展開実証事例|詳細資料はこちらからダウンロード
日本円ステーブルコインJPYCのリスクと注意点とは?

JPYCは多くのメリットを提供する一方で、事業として導入を検討する際には、潜在的なリスクや注意点を客観的に評価し、対策を講じることが不可欠です。リスクは主に「価格・流動性」「規制」「技術・運用」の3つの軸で整理できます。
価格乖離・流動性リスク
JPYCは1JPYC=1円での価値安定を目指していますが、Uniswapなどの分散型取引所(DEX)における取引価格は、市場の需給バランスによって常に変動します。そのため、一時的に1円から価格が乖離(デペッグ)する可能性があります。
これまでは日本円への直接償還ができなかったため、DEXでの売却が主な換金手段となり、価格乖離が起こりやすい構造でした。しかし、今後、資金移動業者として直接償還が可能になれば、価格が1円を下回った際に「安く買って1円で償還する」という裁定取引(アービトラージ)が働き、価格はより強く1円に安定することが期待されます。それでも、市場の極端な変動時や、特定のDEXで流動性が低い場合には、一時的な価格乖出リスクが残ることは認識しておく必要があります。
規制変更・償還リスク
JPYCの将来性における最大の変数は、規制対応の進捗です。現在進められている第二種資金移動業ライセンスの取得が遅延、あるいは予期せぬ問題が発生した場合、償還可能な新JPYCの提供計画に影響が及ぶ可能性があります。
また、無事にライセンスが取得された場合でも、資金移動業者が発行する電子決済手段には、1回あたり100万円という送金上限額が法律で定められています。この上限は、個人間の送金や中小規模の決済には十分ですが、数百万円を超える企業間決済や金融取引など、大規模なユースケースを想定している場合には大きな制約となる可能性があります。税制についても、将来的に変更される可能性はゼロではなく、常に最新の規制動向を注視する必要があります。
ハッキング・スマートコントラクト脆弱性対策
JPYCを含む全てのデジタル資産は、スマートコントラクトの脆弱性を突いたハッキングのリスクと無縁ではありません。第三者機関による監査はリスクを低減しますが、未知の脆弱性が存在する可能性を完全に排除することはできません。
さらに重要なのは、利用者である企業側のセキュリティ管理です。企業の資産としてJPYCを保有する場合、その管理責任は全面的に企業自身が負います。秘密鍵を個人のPCに保存したり、単独の担当者が管理したりする体制は極めて危険です。内部不正やサイバー攻撃による資産喪失を防ぐため、複数の管理者による承認がなければ送金できない「マルチシグネチャーウォレット」の導入や、厳格な社内規定の整備が不可欠です。
日本円ステーブルコインJPYCと他ステーブルコインの比較

自社の事業に最適なステーブルコインを選定するためには、各銘柄の特徴を正しく比較検討することが重要です。ここでは、国内の主要な選択肢であるJPYCとProgmat Coin、そしてグローバルな米ドル建てステーブルコインとの違いを分析します。
国内他円建てステーブルコイン(Progmat Coin等)比較表
国内の円建てステーブルコインは、主にJPYCが目指す「資金移動業型」と、Progmat Coinに代表される「信託型」の2つに大別されます。両者は法的スキームが異なり、それによって特性も大きく変わります。
| 特徴 | JPYC(資金移動業型) | Progmat Coin(信託型) |
|---|---|---|
| 発行主体 | 資金移動業者(JPYC株式会社がライセンス取得予定) | 信託会社(三菱UFJ信託銀行など) |
| 法的スキーム | 資金移動法に基づく「電子決済手段」 | 信託法に基づく「信託受益権」 |
| 資産保全 | 法律で定められた分別管理・供託 | 倒産隔離された信託財産として保全 |
| 送金上限 | 1回あたり100万円 | 上限なし |
| 主なユースケース | 小売決済、給与支払い、Web3サービス、中小規模B2B決済 | 証券トークン決済(STO)、大規模B2B決済、貿易金融 |
| 対応チェーン | マルチチェーン(Ethereum, Polygon, Astar等) | マルチチェーン(各種主要チェーンに対応予定) |
この比較から、送金上限の有無が決定的な違いであることがわかります。100万円以下の機動的な決済を多数行う場合はJPYCが、100万円を超える大規模な決済や、より高いレベルの資産保全が求められる金融取引にはProgmat Coinが適していると考えられます。
USDC・USDTとの為替コストとユースケース比較
グローバル市場ではUSDCやUSDTといった米ドル建てステーブルコインが主流ですが、日本企業が利用する際には無視できない課題があります。
- 為替コストとリスク:日本円建ての事業活動でUSDCを利用する場合、必ず「円→ドル」「ドル→円」の為替交換が発生し、その都度手数料がかかります。また、常に為替変動リスクにさらされ、会計処理も複雑になります。日本円ステーブルコインを使えば、これらのコストとリスクを完全に排除できます。
- 規制環境:日本円ステーブルコイン(電子決済手段)は、日本の資金決済法に準拠し、発行者や仲介者が金融庁の監督下にあります。一方、海外発行のドル建てコインは日本の法律の直接的な監督下にはなく、法的な位置付けが異なります。コンプライアンスの観点からは、国内法に準拠した円建てコインの方が、日本企業にとってはるかに透明性が高く安心です。
- 流動性とユースケース:グローバルな暗号資産取引や海外DeFiでの運用が主目的であれば、依然として流動性が圧倒的に高いUSDCやUSDTが有利です。しかし、国内の決済や送金、円建て資産の取引が目的であれば、日本円ステーブルコインが最適です。
選定チェックリスト:どのステーブルコインを採用すべきか
自社のニーズに合ったステーブルコインを選ぶために、以下の点を検討してください。
- 目的1:大規模な企業間決済(100万円超)や証券決済がしたい → Progmat Coinのような信託型ステーブルコインが第一候補です。
- 目的2:小売決済や従業員への報酬支払いなど、100万円以下の機動的な決済がしたい → JPYCのような資金移動業型ステーブルコインが適しています。
- 目的3:とにかく為替リスクをなくし、会計処理を簡素化したい → 日本円ステーブルコイン全般(JPYC, Progmat Coin等)の採用を強く推奨します。
- 目的4:グローバルな暗号資産取引や海外DeFiでの資金運用がしたい → USDCやUSDTなどの米ドル建てステーブルコインが依然として必要です。
日本円ステーブルコインJPYCの購入から利用までの流れ

日本円ステーブルコインの概念を理解したら、次はいよいよ導入に向けた具体的な実務フローの確認です。ここではJPYCを例に、法人が購入し、管理・利用するまでの流れと、特に重要な会計・税務上の処理について解説します。
JPYC購入方法:取引所・販売所・OTC
償還可能な新しい「電子決済手段」としてのJPYCは、ライセンスを持つ事業者を通じて購入することになります。購入チャネルは主に以下の3つです。
- 販売所:JPYC社自身や提携する事業者から、提示された価格で直接購入する方法です。操作が簡単で初心者向けですが、手数料が価格に含まれている場合があります。
- 取引所:他のユーザーと板取引形式で売買する方法です。価格変動がありますが、販売所より有利な価格で購入できる可能性があります。
- OTC(Over-the-Counter)取引:数千万円以上といった大口の取引を行う場合に、発行者や専門ブローカーと直接相対で取引する方法です。市場価格への影響を抑え、有利な条件で取引できます。
どの方法で購入する場合でも、法人の場合は登記簿謄本などの提出を含む厳格な本人確認(KYC/AML)手続きが法律で義務付けられています。
ウォレット設定とブリッジ手順
購入したJPYCを安全に保管・管理するためには、適切なウォレットの設定が不可欠です。企業が利用する場合、個人の利用で一般的なMetaMaskのような単独署名のウォレットは、内部不正や秘密鍵漏洩のリスクが高く推奨されません。
企業利用では、複数の管理者の署名がなければ送金できない「マルチシグネチャーウォレット」(例:Gnosis Safe)の導入が必須です。ウォレットを作成したら、JPYCのトークンコントラクトアドレスをインポートすることで、残高を管理できるようになります。
また、異なるブロックチェーン間でJPYCを移動させるには「ブリッジ」というサービスを利用します。例えば、イーサリアム上のJPYCを手数料の安いPolygonに移動させることで、送金コストを大幅に削減できます。
実務フロー:会計処理・税務・KYC
経理・法務部門の理解を得る上で、会計・税務上の取り扱いが明確であることは極めて重要です。この点において、日本の「電子決済手段」は大きな優位性を持ちます。
- 会計処理:企業会計基準委員会(ASBJ)の指針により、電子決済手段は時価評価の対象外とされ、額面価額(簿価)で資産計上されます。これにより、価格変動による評価損益が発生せず、決算書の安定化に繋がります。 【仕訳例:100万円で100万JPYCを購入した場合】 (借方) 電子決済手段 1,000,000円 / (貸方) 現金預金 1,000,000円
- 税務処理:
- 法人税:会計処理と同様に、期末の時価評価課税の対象外です。未実現の利益に対して課税されることがなく、税務計算が簡素化されます。
- 消費税:電子決済手段の譲渡は、資金決済法上の定義により「支払手段」の譲渡と見なされ、非課税取引となります。これにより、取引の都度、消費税を計算する必要がなくなり、経理業務の負担が大幅に軽減されます。
これらの明確なルールは、日本企業がデジタル資産を本格的に事業活用するための大きな追い風となっています。
日本円のステーブルコインに関するFAQ(よくある質問)

JPYCは日本円に償還できる?手数料と日数は?
はい、償還できます。ただし、JPYCのバージョンによります。
JPYC社が第二種資金移動業のライセンスを取得した後に発行される新しい「電子決済手段」としてのJPYCは、1JPYC=1円での日本円への償還が法的に保証されます。償還手続きは発行者のウェブサイトなどから行い、銀行振込で受け取ることになります。手数料はブロックチェーンのガス代や銀行振込手数料などの実費が中心となり、日数は数営業日以内が想定されます。
資金決済法に違反しないためのチェックポイントは?
企業がコンプライアンスを確保するためには、以下の3点が重要です。
- 取引相手のライセンス確認:ステーブルコインの発行者が「銀行・信託会社・資金移動業者」のいずれか、取引業者が「電子決済手段等取引業」の登録を金融庁から受けているかを確認します。
- 本人確認(KYC)への協力:法人のKYC手続きは法律で義務付けられているため、登記簿謄本などの必要書類を準備し、適切に対応します。
- 送金上限の理解:資金移動業者が発行するステーブルコイン(新JPYCなど)には1回100万円の送金上限があるため、自社のユースケースがこの制約に収まるかを確認します。
Progmat Coinとの主な違いは何か?
最も大きな違いは、法的スキームとそれに伴う送金上限の有無です。
JPYC(資金移動業型)は100万円の送金上限があり、小売決済やWeb3サービスなど機動的なユースケースに向いています。一方、Progmat Coin(信託型)は送金上限がなく、倒産隔離という高い資産保全性が特徴で、証券決済や大規模な企業間取引といった金融インフラとしての利用を主眼に置いています。
DeFiで利用する際のスマートコントラクトリスクは?
はい、顕著に存在します。JPYC自体の安全性が高くても、それを利用するDeFiプロトコル(分散型取引所やレンディングサービスなど)のスマートコントラクトに脆弱性があれば、資産を失うリスクがあります。
企業の資金をDeFiで運用する際は、そのプロトコルのセキュリティ監査レポートの確認、運用実績、保険の有無など、徹底したデューデリジェンスが不可欠です。あくまで自己責任の世界であることを理解する必要があります。
日本円ステーブルコインについてまとめ
今回、Pacific Meta Magazineでは、日本円ステーブルコインについて以下の内容について紹介してきました。
- 日本円ステーブルコインは改正資金決済法下の「電子決済手段」として定義され、価格安定メカニズムにより1コイン≒1円の価値を維持する。
- 企業にとってのメリットは、コスト削減、24時間365日の即時決済、そして為替リスクの排除と会計処理の簡素化にある。
- 国内ではJPYC(資金移動業型)とProgmat Coin(信託型)が主要プレイヤーであり、送金上限やユースケースによって選択肢が異なる。
- 法人利用では、ライセンスを持つ事業者との取引、マルチシグウォレットによる厳格な管理、会計・税務ルールの遵守が不可欠。
日本円ステーブルコインは、もはや投機的な暗号資産ではなく、国内法に準拠した実用的な「デジタル通貨」としての地位を確立しつつあります。特に、為替リスクの排除と会計・税務処理の簡素化は、これまでデジタル資産の導入をためらってきた日本企業にとって、大きな変革をもたらす可能性を秘めています。
いきなり大規模な導入を目指すのではなく、まずはサプライヤーへの小口支払いや、社内インセンティブプログラムなど、限定的な範囲でのパイロットプロジェクトから始めてみてはいかがでしょうか。その効果と課題を実地で検証することが、この新しい技術を自社の競争力へと転換させるための、最も確実な第一歩となるでしょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
「Web3って何ができるの?」「ブロックチェーンは自社ビジネスに本当に役立つの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。Pacific Metaでは、各社の要望や課題に応じてカスタマイズしたWeb3コンサルティングを提供しています。以下のようなご相談をお受けしております。
- Web3技術の活用方法がわからない
- ブロックチェーン導入の費用対効果を知りたい
- NFTを活用したマーケティング施策を検討している
- グローバル展開におけるWeb3活用のアドバイスが欲しい
個別相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。